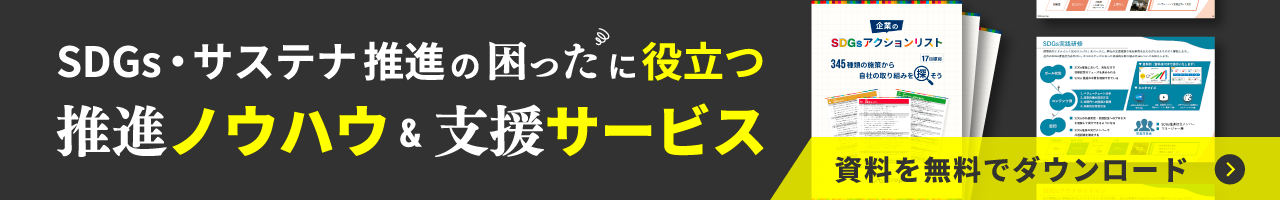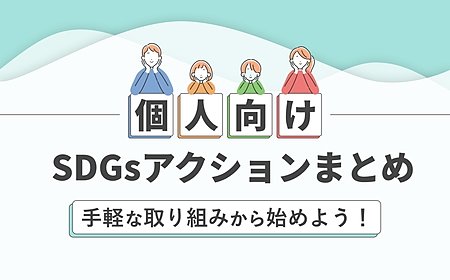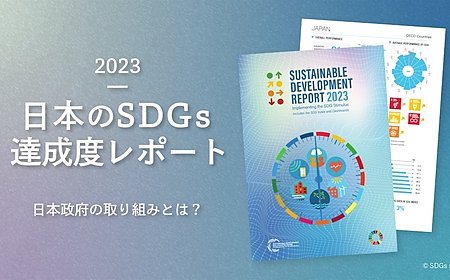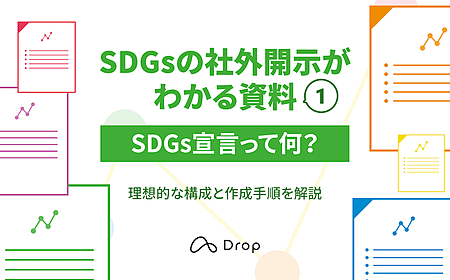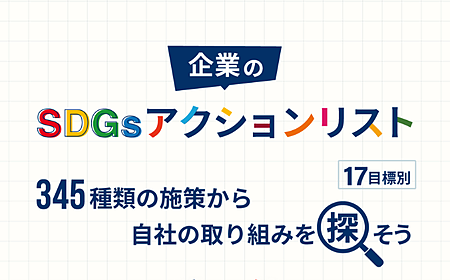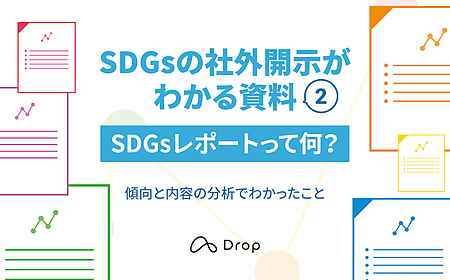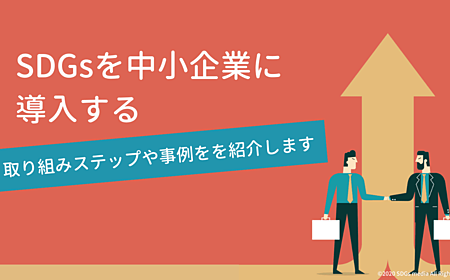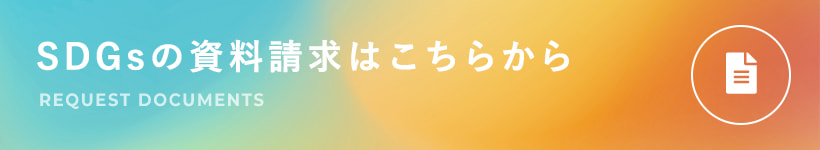バリアフリーを阻む4つの社会的バリアと対策|問題点を紹介

バリアフリーという言葉に聞き覚えがあっても、実際に何が行われているのか具体的なことは知らないという方もいるのではないでしょうか? 段差をなくすという意味だと認識している方が多いかもしれません。
今回の記事では、バリアフリーがどのようなものかについて漠然と捉えている方に向けて、バリアフリーとはなにか、社会にある4つのバリア、バリアフリー新法の趣旨や仕組み、バリアフリーの問題点について解説します。
今回の記事はこんな人にオススメです
- バリアフリーの意味を理解したい
- 法律で規定されているバリアフリーの情報を知りたい
- バリアフリーの問題点や現状を知りたい
目次
バリアフリーとは
バリアフリーとは、日常生活を送るうえで妨げとなる障壁(バリア)を取り除く(フリー)ことで生活しやすくする考え方です。
もともとは建物の入り口や床の段差、道路の段差などを取り除く意味として、建築業界でバリアフリーという言葉が使われていました。現在では、建物の段差のような物理的な障壁だけではなく、社会的・心理的・制度的な障壁を取り除く意味でも用いられています。
街中のバリアフリーの種類
街中には、障害のある方が暮らしやすくなるために、さまざまな工夫が施されています。バリアフリーの一例としては以下のようなものがあります。
- エレベーター
- ホームドア
- 点字ブロック
- 多目的トイレ
- 通路
具体的にどのようなバリアフリーへの取り組みが行われているのかを紹介します。
エレベーター
エレベーターでは、車いすの方でも利用しやすいようにボタンを低い位置に設置したり、車いすの向きを変えなくても出入り口を確認できるように鏡を設置したりしています。
ホームドア・点字ブロック
駅のホームにホームドアや点字ブロックを設置することで、目の不自由な方が誤って線路へ転落したり電車と接触したりしないようになっています。
多目的トイレ
多目的トイレには、車いすの方や排泄機能に障害のあるオストメイトの方、赤ちゃんを連れた方などのためにさまざまな設備が設置されています。
通路
車いすの方や足が不自由な方のために、段差のない通路やスロープを設けることで歩きやすくしています。
心のバリアフリーとは
心のバリアフリーは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことだと、ユニバーサルデザイン2020行動計画で定義されています。
下記のような場面に遭遇した際、見て見ぬふりをしていることはないでしょうか?
- 車いすの方が段差を越えられなくて困っている
- 電車の中で杖をついた方が立っている
- マタニティマークを付けた方がつらそうにしている
困っている方が、何に対して困っているのか、どうすれば解決するのかを相手の立場になって考え行動することが心のバリアフリー実現への第一歩です。
社会にある4つのバリア
障害のある方たちは社会にあるさまざまなことに対してバリアを感じています。社会には以下のようなバリアが存在しています。
- 物理的なバリア
- 制度的なバリア
- 文化・情報面でのバリア
- 意識上のバリア
具体的にどのようなバリアなのかを解説します。
物理的なバリア
物理的なバリアとは、主に移動に関するものになります。以下のようなものが物理的なバリアの一例です。
- 路上に放置されている自転車
- 狭い通路
- ホームと電車の隙間
- 建物の入り口の段差
- 滑りやすい床
- 届かない位置にあるボタン
制度的なバリア
制度的なバリアとは、障害があることを理由として行動を制限されることです。以下のようなものが制度的なバリアの一例です。
- 車いすの方が資格試験を受験できないなどの制限を受ける
- 盲導犬を連れた方が飲食店で入店を断られる
文化・情報面でのバリア
文化・情報面でのバリアとは、障害があることによって情報が十分に得られないことです。
タッチパネルは視覚が不自由な方には使えず、聴覚が不自由な方は音声の案内は聞こえません。障害のある方にとって、このような状況では、必要な情報が得られず困ってしまいます。
意識上のバリア
意識上のバリアとは、差別や偏見、無関心などによって障害のある方を受け入れなかったり、行動を妨げたりすることです。
精神障害を抱える方に対して、何をされるかわからないから怖いと決めつけたり、点字ブロックの上に無意識に物を置くなどして、視覚が不自由な方の歩行を妨げたりすることが意識上のバリアとなります。
バリアフリー新法とは
バリアフリー新法とは、バリアフリー施策を維持するためにハートビル法と交通バリアフリー法を統合したものです。正式な名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」で、2006年6月21日に公布され、同年12月20日に施行されています。
バリアフリー新法の趣旨
バリアフリー新法は、高齢者・障害のある方・妊婦・けが人などの移動や施設利用の利便性や安全性の向上を目的としています。公共交通機関・建築物・公共施設におけるバリアフリー化の促進と、駅を中心とした地区と高齢者や障害のある方などが利用する施設が集まっている地区の重点的なバリアフリー化の促進が行われています。
バリアフリー新法の基準
バリアフリー新法では、建築物や公共交通機関などを新設する際に、バリアフリー化基準へ適合することを義務付けています。また、既存の施設に対しても基準への適合努力義務が課されています。
それぞれの施設におけるバリアフリー化基準の一例を紹介します。
公共交通機関に共通した基準
- 鉄道(鉄軌道)・バス・船舶・航空機には、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を備えること
- 鉄道(鉄軌道)・バス・船舶には、車いすスペースを設置すること
- 鉄道(鉄軌道)・船舶内のトイレには、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること
建築物の基準
延べ床面積の合計が2,000平方メートル(公衆便所については50平方メートル)以上となる特別特定建築物を新築・増築・改築工事する場合には、建築物移動等円滑化基準に適合することを義務付けています。既存の建築物については基準に適合するように努力義務とされています。
特別特定建築物の概要
- 百貨店・劇場・ホテルなどの不特定かつ多数の者が利用する建築物
- 主として高齢者、障害のある方などが利用する老人ホーム・特別支援学校・官公署など
建築物移動等円滑化基準の概要
- 車いす使用者と人がすれ違う廊下の幅を確保する
- 車いす使用者用のトイレがひとつ以上はある
- 目の不自由な方なども利用しやすいエレベーターがある
バリアフリーの問題点

バリアフリーの問題点として以下の2点が挙げられます。それぞれの具体的な内容を解説します。
整備が遅れている
バリアフリー新法によって、市町村は国の基本方針をもとに、バリアフリー化に関する基本構想の作成に努めるようにされています。そのため、各市町村ではバリアフリーに対する取り組みが行われていますが、バリアフリーの整備が遅れている自治体も多いようです。
2019年3月末時点の国土交通省の調査によれば、基本構想の作成を担当する部署があると答えた自治体は、回答自治体数1,387のうち370で約26.9%、ないと答えた自治体は1,004で約73.1%になっています。
基本構想の策定予定がないと回答した市町村に関する調査では、基本構想の策定予定がない理由として以下のような回答があり、担当者不足・予算不足が問題となっています。
| 理由 | 回答者の割合 |
|---|---|
| 利用者が少なく、面的なバリアフリーのニーズが低い | 25.4% |
| 基本構想作成(検討)のための予算が不足している | 24.7% |
| 関係部局の理解・協力が得られない | 20.8% |
| 基本構想に位置付ける事業の実施のための予算が不足している | 18.6% |
ソフト面のバリアフリーが進んでいない
東京都では、福祉のまちづくり条例を制定し、施設整備などハード面のバリアフリー整備だけでなく、心や情報といったソフト面のバリアフリー整備の取り組みも行っています。
しかし、現状としてはソフト面のバリアフリーに対する取り組みは、十分には進んでいません。
この状況は、東京都福祉のまちづくり推進協議会が2015年10月に公表した、東京都における心のバリアフリーに関する調査結果から読み取れます。
調査結果を見た限りでは、手助けが必要な場面に直面した場合に具体的にどうすれば良いかわからない人がまだまだ多いことがわかります。
障害者と付き合う中で、戸惑ったり悩んだりした経験
| 回答 | 回答者の割合 |
|---|---|
ある | 60.8% |
| ない | 21.6% |
| どちらとも言えない | 17.6 |
外出時に困っている人を見かけたときの行動
| 回答 | 回答者の割合 |
|---|---|
| 積極的に自ら手助けをした | 58.1% |
| 相手から求められて手助けをした | 7.8% |
| 手助けまでに至らなかった | 17.0% |
| 何もしなかった | 15.4% |
困っている人を見かけたときに何もしなかった理由
| 回答 | 回答者の割合 |
|---|---|
| 手助けをしてもいいか分からなかった | 35.4%% |
| 忙しかった、急いでいた | 12.6% |
| 他の人が手助けをすると思った | 8.7% |
まとめ
バリアフリーとは、日常生活を送るうえで妨げとなる障壁を取り除くことで、障害のある方でも安心して生活出来るようにする考え方です。物理的なバリアフリーだけではなく制度的・情報的・意識的なバリアフリーに対しても取り組みが行われています。
バリアフリー新法の制定により、全国の地方自治体においてバリアフリーに対する取り組みが行われていますが、担当者や予算が不足して整備が遅れている、手助けが必要な場面に直面した場合にどうしてよいか分からないといった問題もあります。
この記事から得られた情報をもとに、ぜひ日頃からよりバリアフリーに関心を持ち、困っている人がいればどのように手助けやコミュニケーションを取ればいいのか、自身で考えたり身近な人と話し合う機会を設けてみてはいかがでしょうか。
お役立ち資料プレゼントのお知らせ
SDGs研修・eラーニングやSDGsコンサルティングサービスを提供する株式会社Drop(SDGs media運営)では、企業がSDGsに取り組む際に役立つ資料を無料でご提供しています。気になる資料をクリックして資料請求フォームよりお問い合わせください。
[お役立ち資料タイトル]・SDGs社内浸透施策 具体例30選
・SDGs研修の検討・比較ツール
・SDGs/サステナ社内浸透の研修計画作成ツール
・SDGs推進担当者が初めに知っておくべきこと
・SDGsをビジネスに取り込む手順書
・SDGsの社外開示がわかる資料1「SDGs宣言って何?」
・SDGsの社外開示がわかる資料2「SDGsレポートって何?」
・【17目標別】企業のSDGsアクションリスト|345種類の施策から自社の取り組みを探そう
[株式会社Dropのサービス資料]
各種研修・ eラーニング・コンサルティングサービスの資料もご用意しています。必要な資料を以下のページで選択してお問い合わせください。
▶資料請求はこちら
参考サイト: