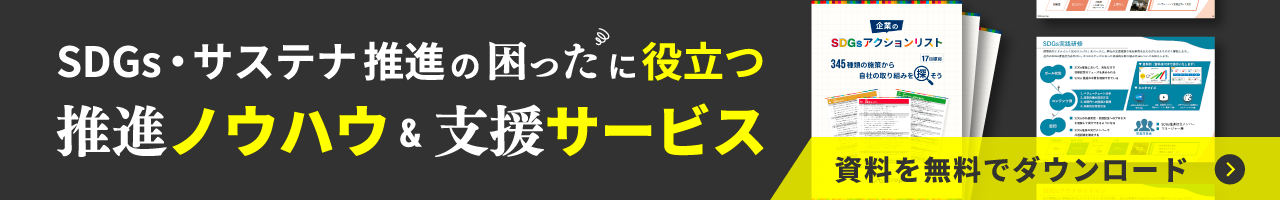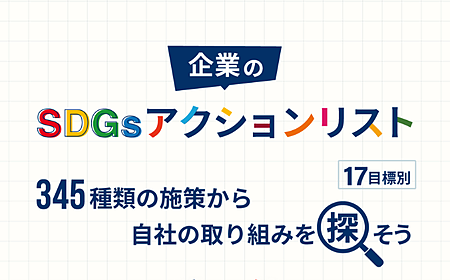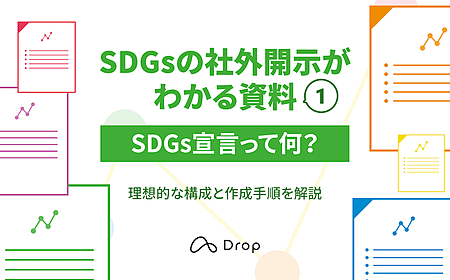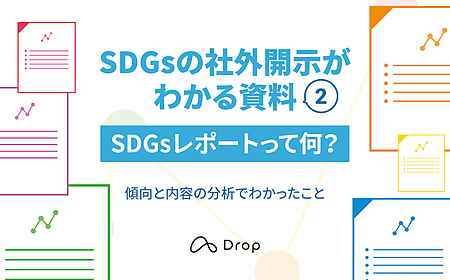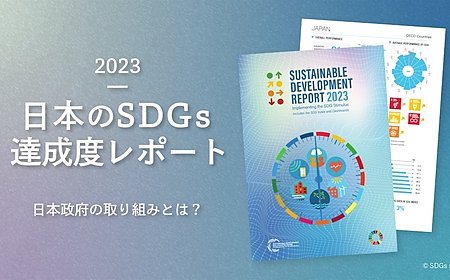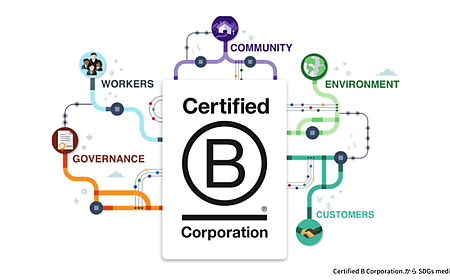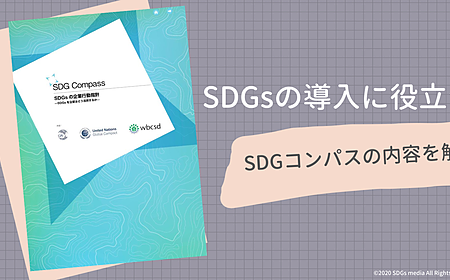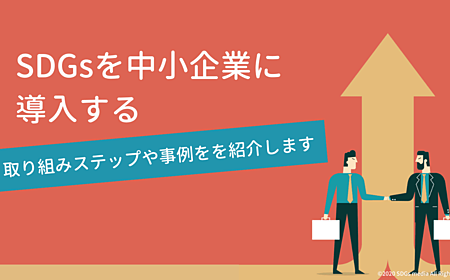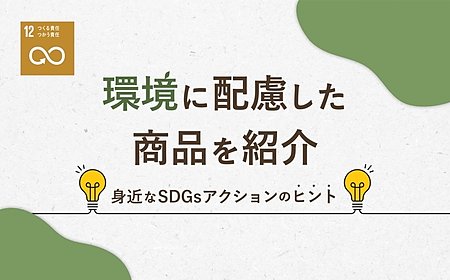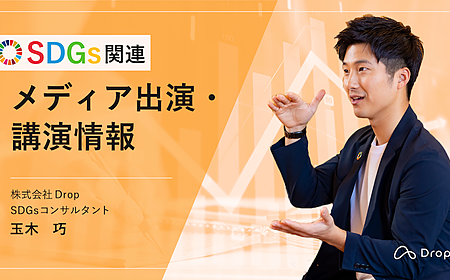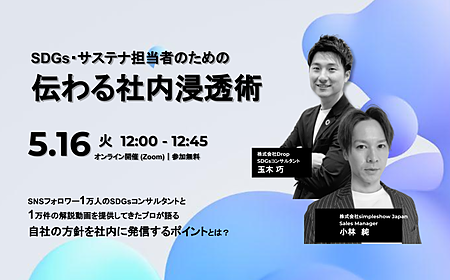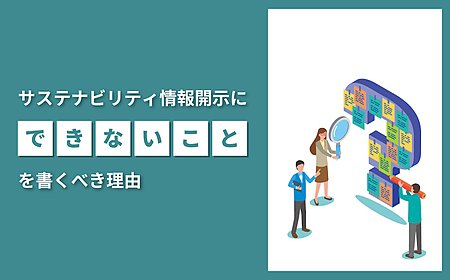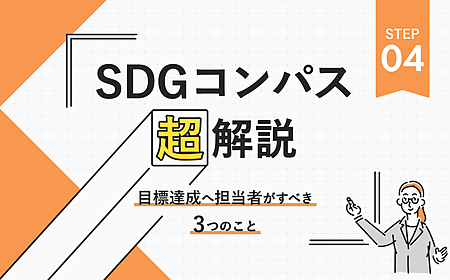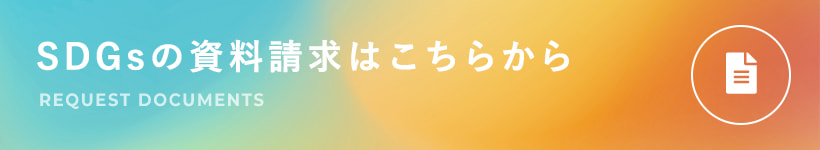サプライチェーンマネジメントとは?導入のメリットや課題を解説

製造業に携わる方であれば、サプライチェーンという言葉を耳にすることも多いと思います。人々の生活や仕事が多様化する現代社会では、さまざまなニーズに応えるためにも、業務効率化を図るサプライチェーンの考え方を理解することが欠かせません。
そこで今回は、製造業だけでなく他の業界で働く方にも向けて、サプライチェーンの概要や特徴についてご紹介します。後半には、サプライチェーンの考え方を取り入れた経営管理手法であるサプライチェーン・マネジメントについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
今回の記事はこんな人にオススメです
- サプライチェーンについて調べていた
- バリューチェーンとの違いを知りたい
- サプライチェーン・マネジメントの導入を検討している
目次
サプライチェーンとは
サプライチェーン(Supply Chain)とは、直訳すると供給の連鎖という意味であり、商品や製品が消費者の手元に届くまでの流れを指す言葉です。
食品や衣類、電化製品などは、さまざまな原材料や部品などから製造され、デパートやコンビニなどの小売業者や問屋へと卸されます。消費者はそれらの商品を、小売店をはじめとした販売店で購入できます。
つまり、消費者が商品を購入するには「原材料・部品調達→生産→物流・流通→販売」という一連の流れが存在し、この流れを称してサプライチェーンと呼んでいます。
サプライチェーンを理解する上で大切なポイントは、サプライチェーンは自社だけでなく、協力関係にある他企業も含めて考えることです。例えば電化製品のメーカーであれば、製品の製造・開発は自社で行い、消費者への販売は卸業者や小売業者などを介して行うことが一般的です。
このように、製品が消費者の手元に届くまでに相互協力的な役割を持つさまざまな業者が介入することで、サプライチェーンは構成されています。
サプライチェーン内の情報の特徴
サプライチェーン内の製品は、生産者から消費者へと流れていきます。その一方で、実際に製品を使用したユーザーの口コミや感想などの情報は、消費者から生産者へと流れていきます。つまり、サプライチェーンにおける製品と情報は、それぞれ逆方向に流れているのです。
口コミや感想などの情報は、製品の品質向上やマーケティング戦略として有効活用できます。このような情報を収集・蓄積して製品の改善につなげられることもまた、サプライチェーンの特徴といえるでしょう。
【無料資料】SDGs/サステナの社内浸透に役立つ資料&ツールをプレゼント
全社でSDGs/サステナビリティに取り組むには、社内浸透が欠かせません。この社内浸透は担当者が苦労する業務の1つでもあります。
そこで、企業内でSDGs/サステナの社内浸透させる際に役立つ資料&ツールを、SDGs media の読者に無料でプレゼントしています。担当者の方はぜひ、以下のお申し込みフォームからお求めください。
サプライチェーンの3つの区分
サプライチェーンは大きく「購買物流」「製造」「出荷物流」の3つに区分できます。ここでは、それぞれの区分の違いについて、自社で製造販売するコットンTシャツを例に解説します。
購買物流
購買物流は、原材料の調達から製造工程に進む前までの区分を指します。Tシャツを作るためには、農家が原材料にあたる綿花を育て収穫し糸にするため紡績工場へ送ります。この段階までが、購買物流の段階です。購買物流は、インバウンド・ロジスティクスやインバウンド・サプライチェーンとも呼ばれます。
製造
製造は、原材料を製品に加工する工程を指します。企業によって関わる工場の数は異なりますが、綿から糸を作り、糸から布を作りTシャツになります。この段階で、製品が完成します。
出荷物流
出荷物流は、製造された製品をエンドユーザーである消費者の手元に届くまでの工程を指します。工場で製造されたTシャツが店頭に並び、消費者に購入される部分に該当します。出荷物流は、アウトバウンド・ロジスティクスやアウトバウンド・サプライチェーンとも呼ばれます。
バリューチェーンとは
サプライチェーンと似ている言葉に、バリューチェーン(Value Chain)というものがあります。バリューチェーンとは、直訳すると「価値の連鎖」であり、企業の事業活動を機能毎に分類し、どの段階でどのような価値が生み出されているのかに着目した考え方です。サプライチェーンは他社を含めた一連の流れで構成されていましたが、バリューチェーンでは自社のみで完結します。
企業の事業活動は、調達・製造・出荷などの物流から、マーケティング活動、アフターサービスまで多岐に渡ります。それら一連の事業活動を通じて、各活動によってどのような価値が生み出されているのかに着目し、競合他社と比較して自社のどの部分に強み・弱みがあるのかを分析することで、事業戦略の有効化を図ります。
バリューチェーンとサプライチェーンは、意味が混同されていることも多いため、どちらの言葉の意味も把握した上で、文脈や場面に応じて使い分けたりどちらの意味が当てはまるのか確認したりすることをおすすめします。
【独自サービス】知識獲得の先にある自社方針の解説を含む貴社オリジナルの動画教材を制作します!
SDGs/サステナビリティの社内浸透には、従業員に基礎知識と自社方針を理解してもらう必要があります。しかし、既存のパッケージ化された研修・ eラーニング教材では、自社方針を盛り込むことが難しいです。
そこでSDGs media を運営する株式会社Dropでは、自社方針の解説などお客様が従業員に知ってもらいたい情報を教材に盛り込める『社内浸透用のオリジナル動画制作サービス』を取り扱っており「自社方針や取り組み内容など社員に伝えたい情報をわかりやすく動画にしてもらえて、繰り返し毎年利用できることも助かる」などと好評を得ています。
サプライチェーン・マネジメントとは
サプライチェーンは製品と情報の流れであると解説しましたが、これら2つの要素を管理する経営手法にサプライチェーンマネジメントと呼ばれるものがあります。
ここでは、サプライチェーン・マネジメントの概要と、多くの企業にサプライチェーン・マネジメントが導入された背景について解説します。
サプライチェーン・マネジメントの概要
サプライチェーン・マネジメント(supply chain management:SCM)とは、サプライチェーン全体で情報を共有・連携して、全体の流れを最適化する経営手法のことをいいます。
サプライチェーンでは、製品が生産者から消費者の手元に届くまでにさまざまな工程を経ていると解説しました。このサプライチェーン内にあるモノとお金の流れを情報と結びつけ、効率的な経営を目指すことが、サプライチェーン・マネジメントの考え方です。
サプライチェーン・マネジメントは、1982年にアメリカのコンサルティング会社ブース・アレン・ハミルトンのK.R.オリバー氏とM.D.ウェバー氏が提唱し、活用されたことが始まりといわれています。
サプライチェーン・マネジメントが導入された背景
サプライチェーン・マネジメントが導入された背景にはいくつかの要因がありますが、その中でも大きな要因として、テクノロジー技術の向上が挙げられます。
2000年代に入り、私たちの生活にはさまざまなITツールが活用されはじめました。多岐にわたる工程を管理することはITツールの得意分野であり、多くの企業がサプライチェーンを一元化できるサプライチェーンマネジメントによる効率的な経営を目指しました。
また、企業のグローバル化に伴うビジネスモデルの変化も、サプライチェーン・マネジメントが導入される一因と考えられます。
たとえば、Amazonをはじめとしたインターネット上の通信販売(EC)が普及し、販売と配送が一体化したビジネスモデルが数多くローンチされています。販売と配送が切っても切り離せない時代となった今、サプライチェーンマネジメントによって一元化した管理体制を構築して、ロスを防ぐことが欠かせません。
さらに日本では、少子高齢化による労働人口減少・人手不足が深刻化しています。移り変わりやすい社会の状況に対応するためにも、サプライチェーンマネジメントを活用して自社の現状を把握し、生産・流通を臨機応変に最適化させることが、安定した経営には欠かせない要素の1つになります。
サプライチェーン・マネジメントのメリット

企業がサプライチェーン・マネジメントを導入することで、大きく以下の3つのメリットを得られます。
- 在庫の最適化によるコスト削減
- 供給スピードの向上
- 人材不足の解消
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
在庫の最適化によるコスト削減
サプライチェーン・マネジメントを導入することで、原材料の仕入れから在庫管理、製造・販売、出荷に渡る物流プロセス全体の最適化を図れます。
特に、製品の在庫管理における需要・供給のバランスは、企業が抱える経営課題の一つです。過剰な在庫は企業のキャッシュフロー悪化の原因になり、その一方で、在庫切れは会社の信用を落とす要因にもつながります。
サプライチェーン・マネジメントによってさまざまな情報を在庫管理と結びつけることで、常に最適な在庫数を把握し、効率よく管理できます。
供給スピードの向上
サプライチェーン・マネジメントによって物流全体を管理することで、各工程のリードタイム(作業の開始から終了までの時間)を削減できます。リードタイムの削減により、市場への製品供給のスピードアップにつながります。
人材不足の解消
人材不足が深刻化しつつある現代社会では、限られた人材の中で効率よく事業を回さなければなりません。そのためには、業務全体の工程を見直し、作業の無駄を省く必要があります。
サプライチェーン・マネジメントを導入することで業務全体の情報管理を行うことができ、必要な工程に必要な人材を配置することで人材リソースを有効に活用できます。
サプライチェーン・マネジメント導入での課題
企業がサプライチェーン・マネジメントを導入するメリットは多くありますが、その一方で、サプライチェーン・マネジメントを導入するにはいくつかの課題が存在します。サプライチェーン・マネジメントの導入を検討している場合は、次にお伝えする2つの課題を事前に把握することで、失敗しないサプライチェーン・マネジメントの導入を目指しましょう。
導入コストがかかる
サプライチェーン・マネジメントを導入するためには、ITシステム導入やインフラ整備などが欠かせません。また、それらを導入・運用するためには専門知識を持った人材が必要になります。そのため、サプライチェーン・マネジメントを導入するためには、多くの導入コストがかかります。
しかし、サプライチェーン・マネジメントの導入によりコストカットが実現して、導入コストの回収までの期間が妥当であれば、十分なメリットが得られます。最近ではクラウドサービスをはじめ、専門知識を持った人材がいなくてもサプライチェーン・マネジメントを導入できる方法もあります。
全体最適を重視しすぎて特定の需要を見逃す
サプライチェーン・マネジメントの導入により業務が効率化する一方で、販売や在庫のデータだけを注視して作業効率化や在庫縮小などを行うと、特定の需要を見逃してしまう恐れがあります。
販売する地域や環境によって人々の生活様式にも違いがあるために、全体のデータだけではなく個別のデータも精査することで、ユーザーの需要を見つけることが重要です。
まとめ
ここまでサプライチェーンの意味と、サプライチェーン・マネジメントの効果や導入時の課題についてご紹介してきました。どの業界の企業であっても1社でビジネスが完結しているわけではなく、自社のサプライチェーン上にはさまざまな企業が関わっています。
サプライチェーン・マネジメントを有効活用することで、自社のサプライチェーンの改善を行い、不測の事態にも対応できる柔軟性を持つことは、先読みが難しい現代には重要な施策です。ぜひ、社内でサプライチェーンの理解を深めるために、今回の記事をご活用ください。
SDGs media 主催のセミナー情報
セミナーの開催予定・申し込みページ
SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。
過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報
過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。
▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら
| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |
|---|---|
| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |
| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |
| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |
| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |
参考サイト:
- 製造業におけるサプライチェーンマネジメントとは?仕組みやメリットを紹介 | デジタルトランスフォーメーション チャンネル
- サプライチェーンとは何か具体例を交えて徹底解説|三井倉庫グループ
- サプライチェーンとは?5つのポイントで理解する物流の話 | クラウドERP実践ポータル
- サプライチェーン|物流用語辞典|株式会社関通
- サプライチェーンとは?バリューチェーンとの違いと意味を図解で比較│ビジネスの教科書
- SCM(サプライチェーン・マネジメント)とは・意味|創造と変革のMBA グロービス経営大学院
- サプライチェーンマネジメント(SCM)とは何か? 基礎からわかる仕組みと導入方法 |ビジネス+IT
- SCMとは?その導入メリットとは?│BizApp チャンネル
- サプライチェーンマネジメント(SCM)で業務プロセス最適化!導入のメリット~見直し手順まで徹底解説 | 人事評価制度の教科書
- SCM(サプライチェーンマネジメント)とは、導入のメリット・デメリットやポイント をご紹介!│顧問派遣のプロフェッショナル人材バンク
- サプライチェーンとバリューチェーンの違い | クラウドERP実践ポータル