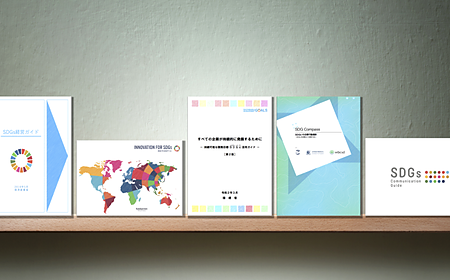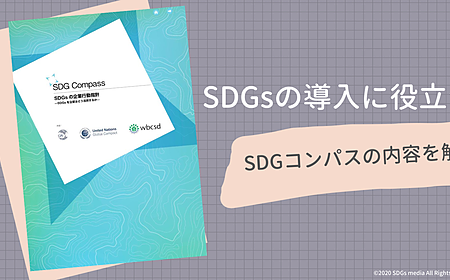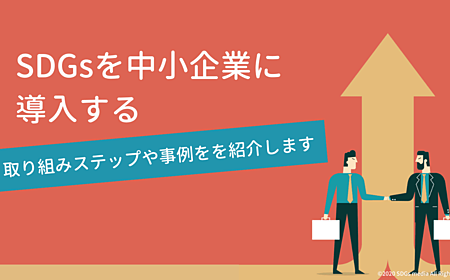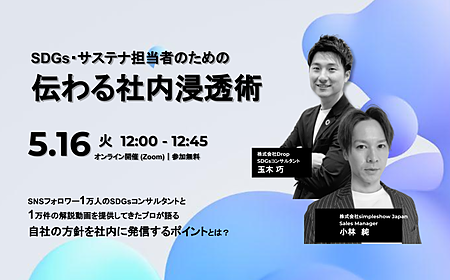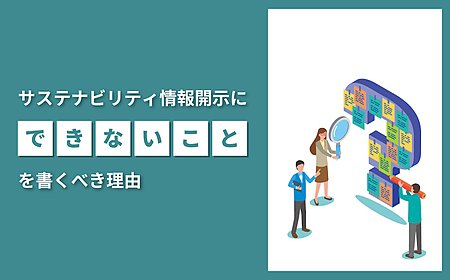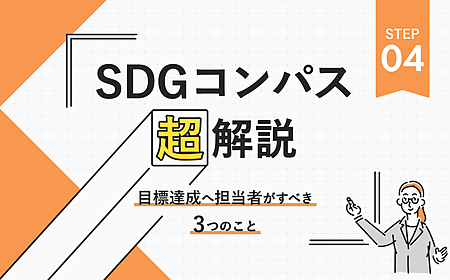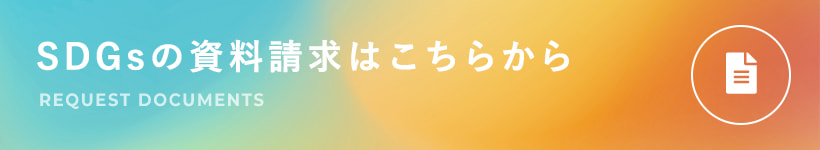SX専門家に聞く「企業のサステナビリティ活動に必要な考え方」

SDGsに取り組みたい企業の担当者や経営層向けに、お役立ち情報を発信しているSDGs media (運営:株式会社Drop)では、2022年8月に出版された『未来ビジネス図解 SX&SDGs』の著者である安藤光展さんにインタビューをしました。
SDGs/サステナビリティ経営の超実践指南書『未来ビジネス図解 SX&SDGs』発売 https://t.co/JzpfltUOC5 pic.twitter.com/O9J8HkCWCl
— PR TIMESビジネス (@PRTIMES_BIZ) August 25, 2022
株式会社Dropの社員が、企業向けにSDGs研修・eラーニング・コンサルティングなどを提供するなかで現場でよく聞くお悩みや、SDGs media のメルマガ読者から集めた質問を安藤さんに聞きました。
SDGs推進に悩むビジネスパーソンに知ってもらいたいお話がたくさん聞けたので、3回に渡ってその内容を紹介します。今回はその第1回の記事です。
SX専門家 安藤さんへのインタビュー記事シリーズの内容
▶第1回:企業がサステナビリティに取り組む意義と身の丈にあった活動(今回はこちら)
▶第2回:マテリアリティの決定・ガイドライン活用のコツ・読者からの質問
▶第3回:KGI・KPIと目標設定・全社的な推進に不可欠な理解と仕組み
安藤 光展さんのプロフィール

サステナビリティ・コンサルタント。一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会・代表理事。専門は、サステナビリティ経営、ESG情報開示。「日本のサステナビリティをアップデートする」をミッションとし、上場企業を中心にサステナビリティ経営支援を行う。日本企業のサステナビリティ経営推進、ESG情報開示支援、マテリアリティ特定支援、レポート/サイトの第三者評価、SDGs対応、GRIスタンダード対応、など支援実績多数。
各種メディアでサステナビリティについての寄稿・取材対応・出演多数。講演実績は直近10年で100件以上。ネット系広告会社などを経て2008年に独立。以降複数の企業の立ち上げを経て、2016年より現職。2009年よりブログ『サステナビリティのその先へ』運営。著書は『未来ビジネス図解 SX&SDGs』(エムディエヌ)ほか多数。Twitterアカウント:@Mitsunobu3
聞き手(株式会社Drop 玉木)のプロフィール

新卒より8年間働いた会社でインド・インドネシア・タイなど7ヶ国を販路開拓し、海外展開に奔走。2019年8月に退職。翌月よりインターンシップでアフリカのセネガルへ。
帰国後は株式会社Dropにジョインし、SDGs研修の講師や企業のSDGs推進を支えるコンサルタントを担当。大企業から中小企業へのコンサルティング経験をもとに、これまで40万人以上のビジネスパーソンにSDGs研修を実施。
その他に Voicyパーソナリティー・allbirdsアンバサダー・Schoo講師など、SDGsを軸に多角的に活動を広げる。活動の記録はこちら。
目次
中小企業にもサステナビリティ対応が必要な理由

中小企業(従業員規模100人〜300人)のSDGs担当者から「自社がSDGsに取り組んだところで社会へのインパクトは小さい(温室効果ガスの排出、水資源の保護など)のでコストを投下してまで取り組むべきだとは考えられない」という声をいただきます。
こういった意見をお持ちの方に対して、安藤さんはどのようにサステナビリティの必要性をお伝えしますか?

サステナビリティに取り組むことで、短期的にコストがかかってしまう、だから取り組まないという判断は、そりゃそうですよね。ただ、企業は活動するだけで何らかのコストがかかってしまいます。そして長期的に見た際に、中小企業はサステナビリティに取り組まなくていいかというと、私はそうではないと思っています。
実は、企業の環境活動は法律で定められており取り組まないといけません。地球温暖化対策推進法が、2021年に改正されたことが関係しています。
現時点では取り組まないことに対する明確なペナルティはないものの、例えば労働問題で中小企業だからといって残業時間が違法とされる時間を少し越えてもいいよね、というのが許されないことと、環境活動も同じです。法律によってルールが変わったことで、企業がサステナビリティに取り組む必要があると言えるかもしれませんね。
また、サステナビリティへの取り組みが、リスクではなくビジネス機会になるということをきちんと理解されたほうがいいです。
グローバル企業の動きを見ていると、環境活動をしていない企業はビジネス機会を得られなくなってきています。例えば、Apple社は、一次・二次サプライヤーに対して、高いレベルの環境対応を求めるということを発表しています。なぜなら、環境対応が不十分な企業と取引をしているとApple社のESG評価が下がってしまうからです。これはサステナブル調達や責任ある調達などと言われていることです。
これから先の社会の変化を、会社としてどう考えていくかが重要です。実はサステナビリティへの取り組みには、コストのかからない活動もいっぱいあるので、大企業と同じような取り組みをするのではなく、身の丈にあったことでいいから少しずつ始めようと、私のクライアントにも伝えています。
【独自サービス】知識獲得の先にある自社方針の解説を含む貴社オリジナルの動画教材を制作します!
SDGs/サステナビリティの社内浸透には、従業員に基礎知識と自社方針を理解してもらう必要があります。しかし、既存のパッケージ化された研修・ eラーニング教材では、自社方針を盛り込むことが難しいです。
そこでSDGs media を運営する株式会社Dropでは、自社方針の解説などお客様が従業員に知ってもらいたい情報を教材に盛り込める『社内浸透用のオリジナル動画制作サービス』を取り扱っており「自社方針や取り組み内容など社員に伝えたい情報をわかりやすく動画にしてもらえて、繰り返し毎年利用できることも助かる」などと好評を得ています。
企業の身の丈にあったサステナブルな活動に不可欠な考え方とは?


ご著書のテーマであるSX(サステナブルトランスフォーメーション)では、文字通り「変革」を目指すことが不可欠だと理解しています。ただ、身の丈にあった活動やできることから始めるとなると、本当に変革が起きるのでしょうか?
用語解説:SX(サステナブルトランスフォーメーション)
「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」とは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指す。社会のサステナビリティと企業のサステナビリティの同期化とは、企業が社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味する。
引用元:伊藤レポート 3.0(SX版伊藤レポート)|経済産業省(PDF)

サステナビリティ推進活動において、「できることからやる」と「身の丈に合った活動」は異なります。企業の取り組みが「できることからやる」だとトランスフォーメーションにならず、サステナビリティは推進できないと思っています。
企業が取り組むサステナビリティは、その企業の長期ビジョンやパーパスといった目指す将来から逆算して、いま実践すべきことを考えるアウトサイドインやバックキャスティングの思考が重要です。
しかし、「できることからやる」は、その真逆になってしまいSDGsやサステナビリティのコンセプトに反します。
私の言う「身の丈にあった活動」は、パーパスや企業理念が描く未来から逆算した結果、いま自社にできることをバックキャスティングで考えていくことを前提にしています。この考えなしに「できることからやる」は組織でやってはいけません。例えば、従業員エンゲージメントに関する取り組みなど「身の丈にあった活動」はどんな企業でも1つや2つは見つかるはずだと思います。
中小企業の場合は、トランスフォーメーションを目指しすぎず、バックキャスティングを考える際にトランスフォーメーションの仕組みや方向性を理解するにとどめてもいいでしょう。

身の丈にあったと聞くとネガティブな印象を持たれる可能性もあるかなと思いましたが、そうではないということがよくわかりました。

本にも書きましたが、サステナビリティで重要なものは3つです。パーパス・マテリアリティ・長期ビジョンで、これは経産省やIIRC(国際統合報告評議会)が示すIRフレームワークでも言及されています。
この3つがあってこそサステナビリティの取り組みが進んでいくので、これを前提とした上で、身の丈にあった取り組みを推奨しています。
【無料資料】SDGs/サステナの社内浸透に役立つ資料&ツールをプレゼント
全社でSDGs/サステナビリティに取り組むには、社内浸透が欠かせません。この社内浸透は担当者が苦労する業務の1つでもあります。
そこで、企業内でSDGs/サステナの社内浸透させる際に役立つ資料&ツールを、SDGs media の読者に無料でプレゼントしています。担当者の方はぜひ、以下のお申し込みフォームからお求めください。
責任あるビジネスがサステナビリティへの道につながる?


ダノンのCEO解任などの発表を受けて「ESG対応の先に、サステナビリティの実現はない」という論調や、企業のESG対応が情報開示を重視しているが情報開示だけではサステナビリティに繋がっていないという意見があります。これらについてはどうお考えですか?

ダノンの1社の例で言い切るには短絡的に感じます。サステナビリティを目指す上では、レスポンシビリティ(責任)が重要になってくると思います。例えば、パタゴニアの創業者のイヴォン・シュイナードさんは、インタビューで「サステナビリティは存在し得ない」と言っています。
100年続いている老舗企業であっても、新型コロナウイルスの感染拡大やウクライナ紛争など外部環境の変化によって倒産することもあります。だから10年や100年続くような企業はあっても、未来にわたっていつまでも存続するサステナブルな企業は存在しません。
「環境負荷・社会負荷をかけないことで責任を果たすといったCSRに近い考えとして、責任あるビジネスを追求して実践することでサステナブルな組織を目指そう」という趣旨の話をイヴォン・シュイナードさんはしていて、私も基本的にはこれに賛成しています。
もちろん責任あるビジネスを目指しても、サステナビリティが達成できるかどうかは誰にもわかりません。でもわからないなら、目指すことがまず重要ではないでしょうか。

レスポンシビリティとして責任あるビジネスを実践しながら、その成果となるインパクトを追い求めていくことが、サステナビリティを目指す企業の姿になっていくのでしょうか?

そうですね、最近「リスクと機会」という表現が使われるようになったのは、レスポンシビリティとインパクトが意識されている現れだと感じます。
企業視点で見る物事には、リスク対応と事業機会の両側面があります。リスクだけ見るとその対応に必要なコストだけが発生してしまい、事業機会だけ見ると表面的で中身が伴っていないウォッシュとなるビジネスになってしまうため、どちらの側面も重要です。
役員向けサステナビリティ研修の主題は大局観と経営陣の役割

サステナビリティに消極的な役員に対して、役員研修を実施しようと検討しています。役員研修では何を培ってもらえばいいのでしょうか? また、安藤さんが役員にプレゼンする上で工夫されていることはございますか?

参加する役員のサステナビリティに関する知識レベルや企業が置かれるフェーズによって異なります。一般論ではサステナビリティの大局観・全体的なこととして、いかにサステナビリティが経営に対して重要なのかを理解してもらえるように話をします。
具体的には、パーパス・マテリアリティ・長期ビジョンなどをどう考えていくのかという話題です。
他には、サステナビリティに限らずですが、経営層、特に社長がサステナビリティに向けて動かないと現場は動かないという話をします。現場が主導してボトムアップで実行するにも、社長がそういった動きに対して肯定的でないと成り立たないことを理解してもらいます。
あとは、メガトレンドの話題から社内の動きに合わせた経営判断や、リスクと機会、戦略の重要性などもよく話題に出します。

ご著書の中でも「社長がSDGsの推進している」事実が、現場の取り組みを促進すると書かれていたことが、さまざまなクライアントの現場を見てきた実感と重なって印象に残っています。
企業がSDGs・サステナビリティに取り組むなかで推進委員会をつくるケースが多いと思います。そのトップには社長を据えるべきなのでしょうか?

そのような人選にしていることがほとんどですね。コミットの程度は企業によってさまざまで、年に1回や2回程度だけ委員会に出席して意見交換するだけのような状況もあります。

うまく機能している委員会では、社長はどのように関わっていることが多いですか?

社長が主体的に動いている、もしくは社長自身が率先してアクションを起こさないといけないことを理解されていると、うまく機能しやすいです。

そういう使命感を持ち能動的になってもらうのは、大変じゃないですか?

そうですね…実際はほぼ無理ですね(笑)人が変わるのってすごく難しいもので…。
年齢が高く実績がある社長は特に、自分の価値観を大事にされているので、なかなかこういったことを実践してもらうのは難しいです。
なので、社長が意識を変えてくれるように、コミュニケーションを取っていっていくしかないと思います。それは、私のような支援側の外部コンサルタントだけでなく、社内・現場の人も含めて、社長に具体的な情報を継続的に提供し続けた先に見えてきます。
とはいえ、人の意識を変えるというのは並大抵のことではありません。そのため極端な話、会社のサステナビリティの方向にガラッと変えたいなら、社長を代えるしかないです。

ここまでありがとうございました。次の記事では今回のお話にもあったサステナビリティで重要な要素の1つである「マテリアリティ」についていろいろお話を伺います。
ここまでで話題に出てきた、サステナビリティとSDGsの関係やパーパスについては以下の情報を参考にしてみてください。
SX専門家 安藤さんへのインタビュー記事シリーズの内容
▶第1回:企業がサステナビリティに取り組む意義と身の丈にあった活動(今回はこちら)
▶第2回:マテリアリティの決定・ガイドライン活用のコツ・読者からの質問
▶第3回:KGI・KPIと目標設定・全社的な推進に不可欠な理解と仕組み
今回のインタビュー内容に関連する記事と動画
SDGs media 主催のセミナー情報
セミナーの開催予定・申し込みページ
SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。
過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報
過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。
▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら
| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |
|---|---|
| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |
| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |
| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |
| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |



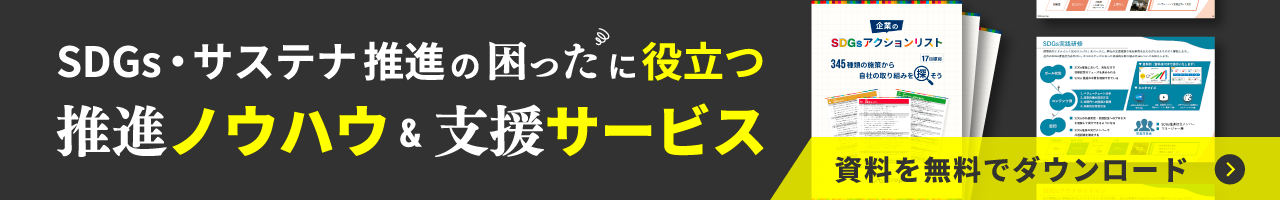



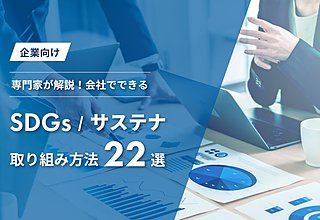


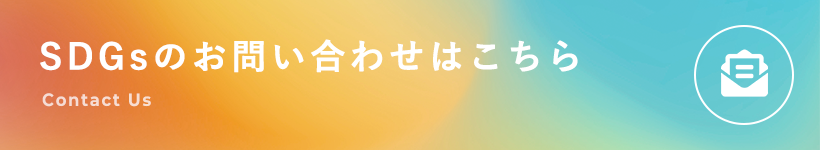




![[サービス紹介]SDGs eラーニング|マイペースで学べる社員研修サービスをリリースの画像](https://sdgs.media/cms/wp-content/uploads/thumb/cms/2021/03/a428fa11fdfdeb8c1526db79e5af4e26-450x280-c.png)