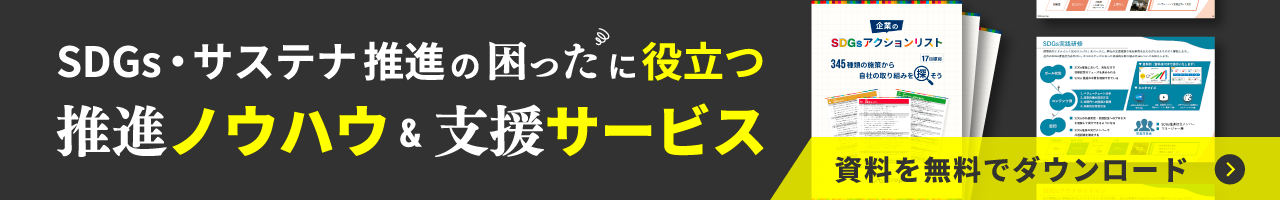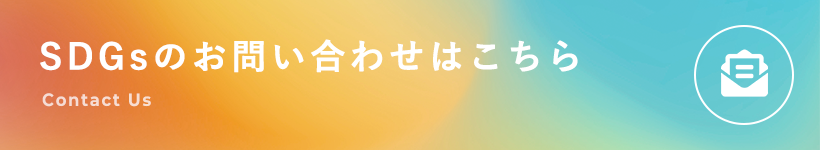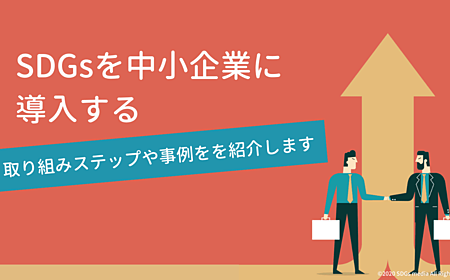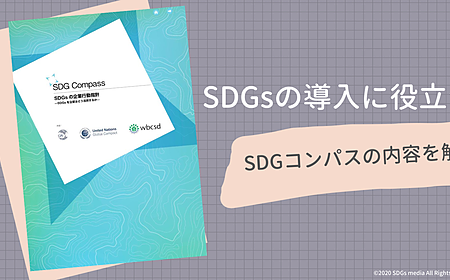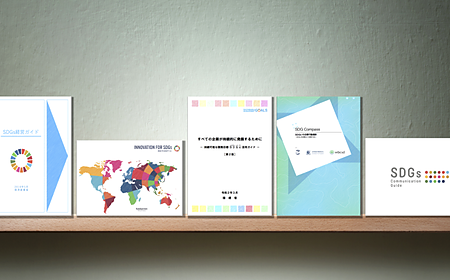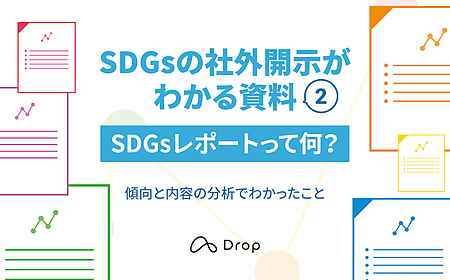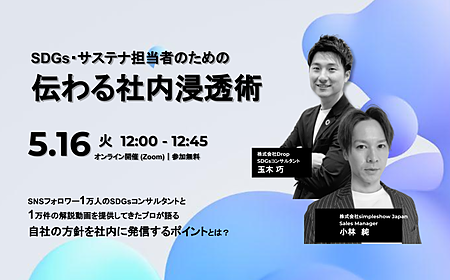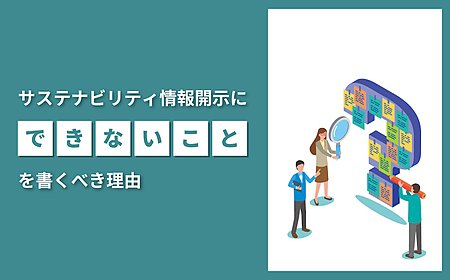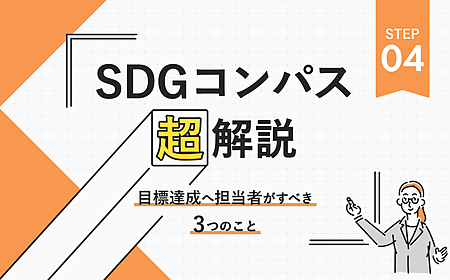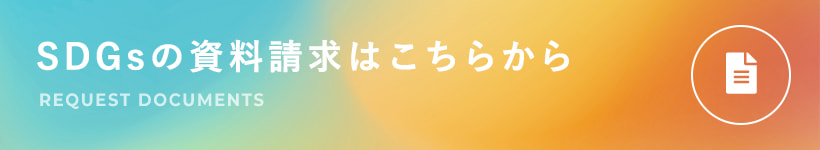SX専門家に聞く「KGIと目標設定、全社的な推進を進めるコツ」

SDGsに取り組みたい企業の担当者や経営層向けに、お役立ち情報を発信しているSDGs media (運営:株式会社Drop)では、2022年8月に出版された『未来ビジネス図解 SX&SDGs』の著者である安藤光展さんにインタビューをしました。
SDGs/サステナビリティ経営の超実践指南書『未来ビジネス図解 SX&SDGs』発売 https://t.co/JzpfltUOC5 pic.twitter.com/O9J8HkCWCl
— PR TIMESビジネス (@PRTIMES_BIZ) August 25, 2022
株式会社Dropの社員が、企業向けにSDGs研修・eラーニング・コンサルティングなどを提供するなかで現場でよく聞くお悩みや、SDGs media のメルマガ読者から集めた質問を安藤さんに聞きました。
SDGs推進に悩むビジネスパーソンに知ってもらいたいお話がたくさん聞けたので、3回に渡ってその内容を紹介します。今回はその第3回の記事です。
SX専門家 安藤さんへのインタビュー記事シリーズの内容
▶第1回:企業がサステナビリティに取り組む意義と身の丈にあった活動
▶第2回:マテリアリティの決定・ガイドライン活用のコツ・読者からの質問
▶第3回:KGI・KPIと目標設定・全社的な推進に不可欠な理解と仕組み(今回はこちら)
安藤 光展さんのプロフィール

サステナビリティ・コンサルタント。一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会・代表理事。専門は、サステナビリティ経営、ESG情報開示。「日本のサステナビリティをアップデートする」をミッションとし、上場企業を中心にサステナビリティ経営支援を行う。日本企業のサステナビリティ経営推進、ESG情報開示支援、マテリアリティ特定支援、レポート/サイトの第三者評価、SDGs対応、GRIスタンダード対応、など支援実績多数。
各種メディアでサステナビリティについての寄稿・取材対応・出演多数。講演実績は直近10年で100件以上。ネット系広告会社などを経て2008年に独立。以降複数の企業の立ち上げを経て、2016年より現職。2009年よりブログ『サステナビリティのその先へ』運営。著書は『未来ビジネス図解 SX&SDGs』(エムディエヌ)ほか多数。Twitterアカウント:@Mitsunobu3
聞き手(株式会社Drop 玉木)のプロフィール

新卒より8年間働いた会社でインド・インドネシア・タイなど7ヶ国を販路開拓し、海外展開に奔走。2019年8月に退職。翌月よりインターンシップでアフリカのセネガルへ。
帰国後は株式会社Dropにジョインし、SDGs研修の講師や企業のSDGs推進を支えるコンサルタントを担当。大企業から中小企業へのコンサルティング経験をもとに、これまで40万人以上のビジネスパーソンにSDGs研修を実施。
その他に Voicyパーソナリティー・allbirdsアンバサダー・Schoo講師など、SDGsを軸に多角的に活動を広げる。活動の記録はこちら。
目次
自社のマテリアリティをKGI・KPIに変換するには?


企業によってマテリアリティに対してKGIを設定するケース、定量的なKGIを設定せずにマテリアリティをゴールとしてマテリアリティに対するKPIを設定するケースのどちらも目にします。
KGIの定義や位置づけに対してわからなさがあるのですが、このあたりはどう理解すればいいでしょうか?
※マテリアリティがわからない場合は、まず前回の記事を読んでください。

捉え方が企業によってそれぞれなので、これって言う決まったものは正直言ってありません。
定義は、マテリアリティを定量化したものがKGIです。理解しておかないといけないのは、マテリアリティの項目名と、マテリアリティがKGIになった場合の項目名は変わることが多いということです。
マテリアリティは抽象的な言葉になりやすいので、達成を目指して測定するには言い換える必要があります。例えば、マテリアリティとして採用する企業が多い「ダイバーシティ推進」を、KGIにすると女性役員数を3人にするなどが考えられます。
このKGIを達成するための指標がKPIなので、女性役員を増やすために女性の部長や課長を増やす、ということがKPIになります。そして、女性の部長・課長を増やすためのTODOや、このKPIを達成するためのKPIが設定されます。
KGIは各社の決め方で考えていくといいですが、なぜその項目がKGIになるのか、どのマテリアリティと関係があるのかなどは、しっかりとステークホルダーに説明して納得を得ることが大切です。

環境に関するKGIは、GRIなど各種ガイドラインを見れば指標を考えやすいのですが、ダイバーシティはすごく難しく感じます。安藤さんはどうやってダイバーシティについて考えていますか?

ダイバーシティ分野では、人数が定量的な指標になります。サステナビリティというよりは、人的資本に対するもので例えば従業員のスキル向上や研修の実施時間など、この方面で考えれば別の指標が見えてきます。
定量的な指標を決めるという点では、ダイバーシティのなかでも女性や障害者に関することは設定しやすいですが、LGBTQに関することは難しいです。会社として誰が当事者なのか聞くことは原則としてできないからです。また承諾を得て聞けたとしても、正確に答えてもらえるかどうかはわかりません。
当事者の把握ができないと個別のアプローチができません。そのため、できることはLGBTQに対する勉強会やアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込みや偏見)を題材に研修をするなどです。ハード面では、性別関係なく使えるトイレを増やすなどは指標になり得ますが、オフィスを賃貸で構えている企業にはあまり現実的ではないでしょう。
そのため、この分野に対しては、例えば定量的な項目は決めないで、エンゲージメントを深めることによって従業員の意識の醸成をしているといった、定性的なプロセスの開示が1つの方法になります。
このような方針をステークホルダーに対して開示して、定量的ではなくとも従業員一人ひとりのためになっている施策であることや、これからより良い指標を模索していくことなどを伝えて、納得してもらうことは目指せるでしょう。
【独自サービス】知識獲得の先にある自社方針の解説を含む貴社オリジナルの動画教材を制作します!
SDGs/サステナビリティの社内浸透には、従業員に基礎知識と自社方針を理解してもらう必要があります。しかし、既存のパッケージ化された研修・ eラーニング教材では、自社方針を盛り込むことが難しいです。
そこでSDGs media を運営する株式会社Dropでは、自社方針の解説などお客様が従業員に知ってもらいたい情報を教材に盛り込める『社内浸透用のオリジナル動画制作サービス』を取り扱っており「自社方針や取り組み内容など社員に伝えたい情報をわかりやすく動画にしてもらえて、繰り返し毎年利用できることも助かる」などと好評を得ています。
自社らしいKGI・目標設定の方法と決める上での期間の考え方

事業機会の面で、企業らしさを盛り込んだオリジナルなマテリアリティや独自のKGI・目標設定はどう決めればいいでしょうか?

これはすごく難易度の高いことですね。独自のマテリアリティやKGI、目標が決まれば、それが競合他社に対する競争優位になります。
そのためには、社内で徹底的に議論する必要があります。企業の強みや独自性は社内である程度は把握しているはずなので、まずはきちんと議論をする。私の経験上、この議論をしないで答えを出す会社がほとんどです。
外部の人を加えて考えていくにも、まずは社内だけでしっかりと議論をして出てきたものを、外部から呼んだ第三者に整理してもらうといいでしょう。見つけることは難しいですが、見つかれば目指す先が決まるのであとは取り組んでいくだけになります。

目標設定もマテリアリティマトリックスと同じように、長期・短期で考えるといいのでしょうか?
KGI設定が難しいから半年や1年先などを期限に、いまできることをKPIに据えて行動して、1年後に長期のKGIを決めればいいという考え方もあります。
KGIを決めるうえで、このあたりのことはどう考えていますか?

目標設定の時間軸は、3年ぐらいで設定している会社は多いです。コロナ禍やウクライナ紛争など社会の大きな変化が起きているので、一旦の目標として中期の目標を決めるのはありだと思います。
ただ、この際も第1回の記事でお話したバックキャスティングで考えることが重要です。5年や10年先を見据えた上で、3年後に目指す位置を決めるような形です。そうすればその3年後から逆算していま設定すべきKGIも見えてきます。

やはりKGI・目標を決める上で基本となるのはバックキャスティングなのですね。

一方で、KPIは1年かけて最善な方法が見つかれば新しい指標に変えても問題ありません。前著「創発型責任経営」で紹介した動的KPIがこの考えのベースになっています。社会は変化していくので、当然、手法となるKPIも変化して当然です。
とはいえ、毎年コロコロと変えることは推奨しません。例えばマテリアリティが3個決まり、この指標としてKPIが10個決まれば、年間で1個や2個のKPIは改めてもいいと思います。
ただし、KPIが変わっていくとそのもとになるKGIの位置づけが難しくなります。このようなケースだと、暫定的な仮のKGIを設定してまずは1年間取り組んでみるしかありません。実行すればKGIとKPIの妥当性が実感としてわかるはずです。

KGIはバックキャスティングで決めていき、現場が実行して達成を目指すKPIは状況次第で改善していくといいのですね。

前回の記事でお話した身の丈にあった活動もこれに当たります。KGIを決められることが理想ですが、決められないのであれば暫定的に決めて問題はありません。ただ、KPIは決まらないと現場が動かないので、しっかりと決めるところは決める。そして実行した上で、変更するのか・継続するのか判断されるといいでしょう。
サステナビリティの取り組みも、社会の変化に合わせていく必要があるので、このようにある程度は柔軟に動いていくことを前提とすることが、現実的だと思います。とはいえ、トラディショナルな企業は、一旦決めた目標を変えることは難しいこともあるでしょう。これは推進担当者ではどうすることもできないので仕方ありません。

そういった場合に、安藤さんはどのようにアドバイスしているのですか?

各指標を変えたいけど変えられない事情がある企業は、社外に開示するKPIと情報を社内だけに留めるKPIと2つを使い分けるのも1つの手です。この場合、前者は見栄えが良い指標や他社も取り組んでいるような指標になり、後者は社内の実情にあった指標になるでしょう。
状況によってはKGIもこのように使い分けて、実践していくことも1つの手です。
【無料資料】SDGs/サステナの社内浸透に役立つ資料&ツールをプレゼント
全社でSDGs/サステナビリティに取り組むには、社内浸透が欠かせません。この社内浸透は担当者が苦労する業務の1つでもあります。
そこで、企業内でSDGs/サステナの社内浸透させる際に役立つ資料&ツールを、SDGs media の読者に無料でプレゼントしています。担当者の方はぜひ、以下のお申し込みフォームからお求めください。
KGI・KPIを全社的に実行するには社員の理解と仕組みが必要


SDGsやサステナビリティ委員会で決めたKGIやKPIを社内の各部署に伝えて実行してもらう際に、各部署を巻き込むコツはありますか?

ある程度の規模の企業であれば、組織体制としてSDGs・サステナビリティの取り組みは委員会をトップとして、そこからトップダウンの形で各部署に落としていく形でいいと思います。その際は、会議を開いて各部署に参加してもらい伝えていきます。
規模が小さい企業であれば、全員でディスカッションして決めていくこともありますが、あまり現実的ではないと思います。
トップダウンで進めていく場合でも、実際にKPIを追っていくなかで起きた現象や結果は、委員会に対してフィードバックしていく体制をつくることは重要です。

これまでの支援経験から、委員会で決めたKPIを各部署に落とし込んでいっても、そのKPIに貢献する具体的な取り組み案が能動的には提案されないこともありました。
各部署の行動を促す方法の1つに、研修など社内浸透策を実施して各部署の知識を増やすことで、能動的な提案を期待することが考えられます。他には何か策があるでしょうか?

各部署が自社のマテリアリティに貢献できるような仕組みを作ることがオススメです。
その1つは、能動的な取り組みに対して、お金や名誉などインセンティブを用意することです。例えば、各部署を対象に社会に貢献する事業のアイデアコンテストを開催して、それぞれに自社が対象とする社会課題(マテリアリティ)に対して、各部署の強みや特徴を生かしたアイデアや仕組みを提案してもらう。
また、1つ前の質問への回答でお話した、各部署から委員会に対して取り組みのフィードバックが上がってくる準備や仕組みを用意することも重要です。事業部は、知識がないからフィードバックできない、フィードバックが見当違いだったら自分の評価が下がるのではないか、といった不安を持っています。これを何らかの形で解消しましょう。
しかし、情報を与えすぎると動けなくなる人もいるので注意が必要です。会社での一つひとつの行動が社会のためにならないといけないと考えすぎることで、何もできず思考停止状態に陥ってしまうおそれがあるからです。
私の経験上、人の意識を変えるのはすごく難しくほぼ不可能です。だから、社内浸透でSDGsの知識を学んでもらうといった情報提供だけでは、各部署の能動的な動きは生まれてこないでしょう。そのため、仕組みを用意してそれに巻き込んでいくことが、1つの正解だと思っています。

新著でも、SX推進には社内の人材開発が必要だと強調されています。人材開発を進めるにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか?

期間に決まったものはなくケース・バイ・ケースですね。短期間で必ずできるというものではなく、少なくとも3年、長いと5年や10年が必要だと思っています。
SXを含めてサステナビリティ推進の知識や実績を持つとなると、これくらいは必要でしょう。これらの知識や実績を持てるようになれば、推進において仮説の精度が上がってくるので、そうなればその人をSX人材だと呼んでもいいと思います。

今回は、たくさんの質問に対して具体的な回答をいただきありがとうございました。
SX専門家 安藤さんへのインタビュー記事シリーズの内容
▶第1回:企業がサステナビリティに取り組む意義と身の丈にあった活動
▶第2回:マテリアリティの決定・ガイドライン活用のコツ・読者からの質問
▶第3回:KGI・KPIと目標設定・全社的な推進に不可欠な理解と仕組み(今回はこちら)
「SDGsが伝わらない!」から脱却する30の社内浸透の方法を資料にまとめました
SDGsに取り組む際の課題の1つとして挙げられる「社内の理解度が低い」。研修・Webや社内報・トップメッセージなどで社内にSDGsを浸透させようとするものの、中間管理職や一般社員のSDGs理解度に課題を抱える担当者は多いです。目指すはSDGsの社内啓蒙を強化することですが、なかなかうまくいかない現実があります。
そのような担当者向けに作成したダウンロード資料が『SDGs社内浸透施策 具体例30選』です。実際に、当社に寄せられる社内浸透へのお悩み、当社の支援実績や企業事例をもとに厳選した30種類の社内浸透策をまとめています。
社内浸透がうまくいっている企業では、1度きりの研修ではなくさまざまな手法で継続的に施策を実行しています。ぜひ資料を参考にして新たな社内浸透の方法を採用して理解度アップにお役立てください。
SDGs media 主催のセミナー情報
セミナーの開催予定・申し込みページ
SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。
過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報
過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。
▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら
| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |
|---|---|
| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |
| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |
| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |
| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |