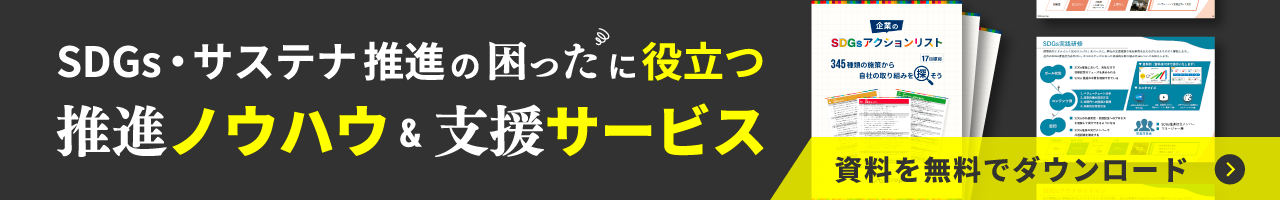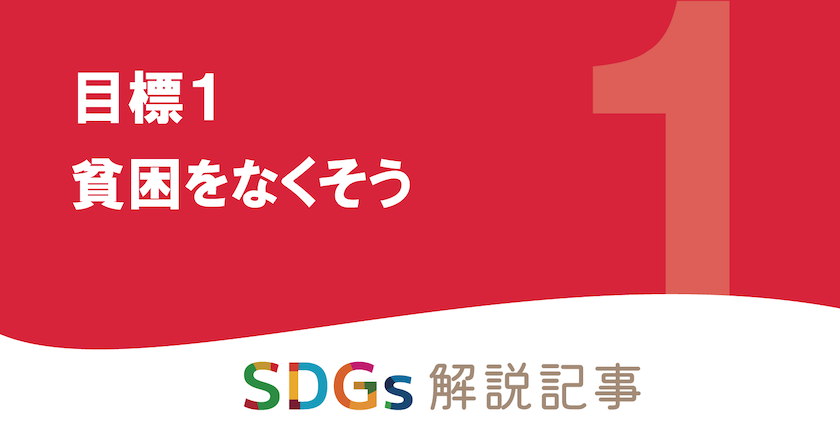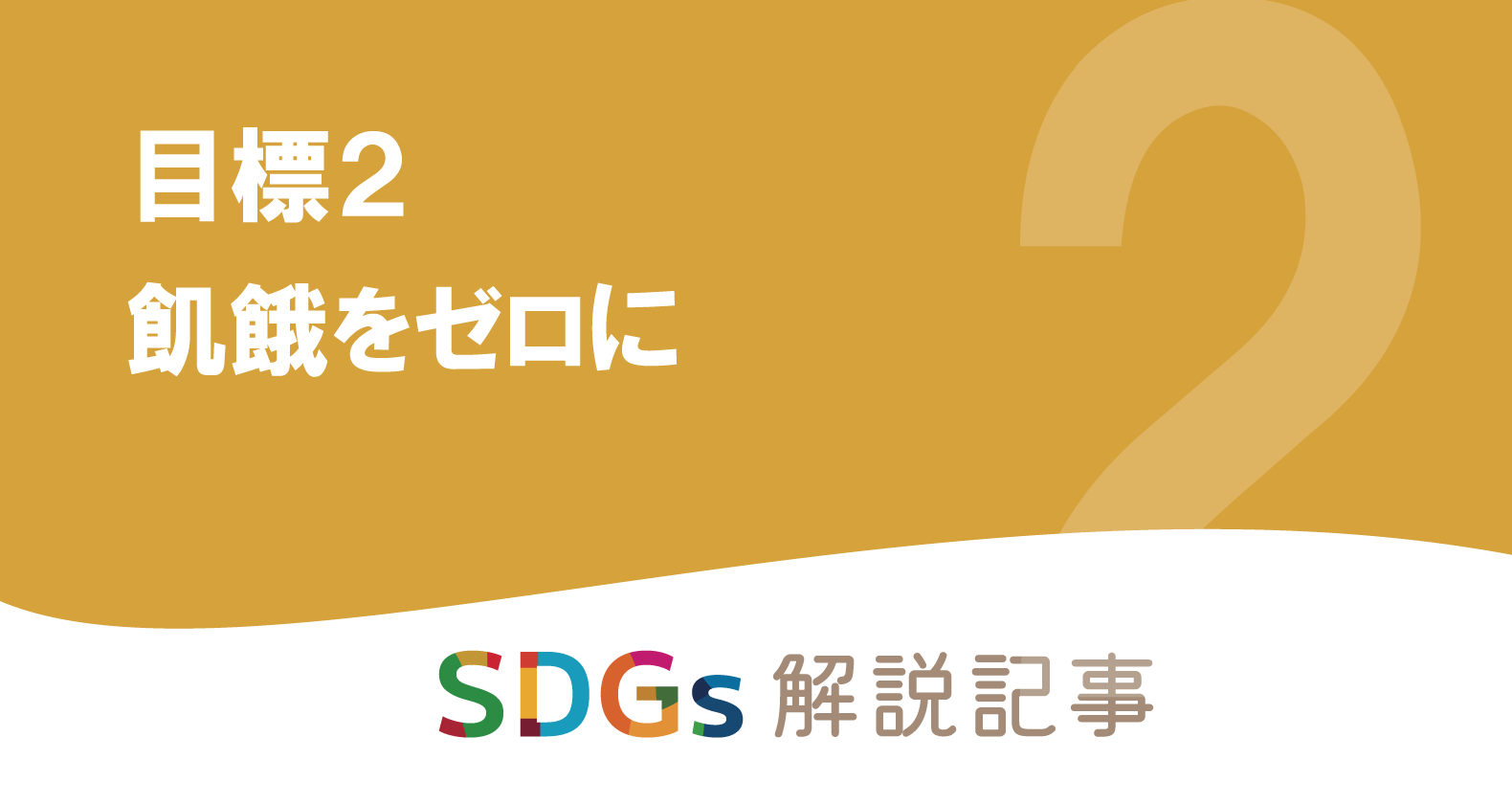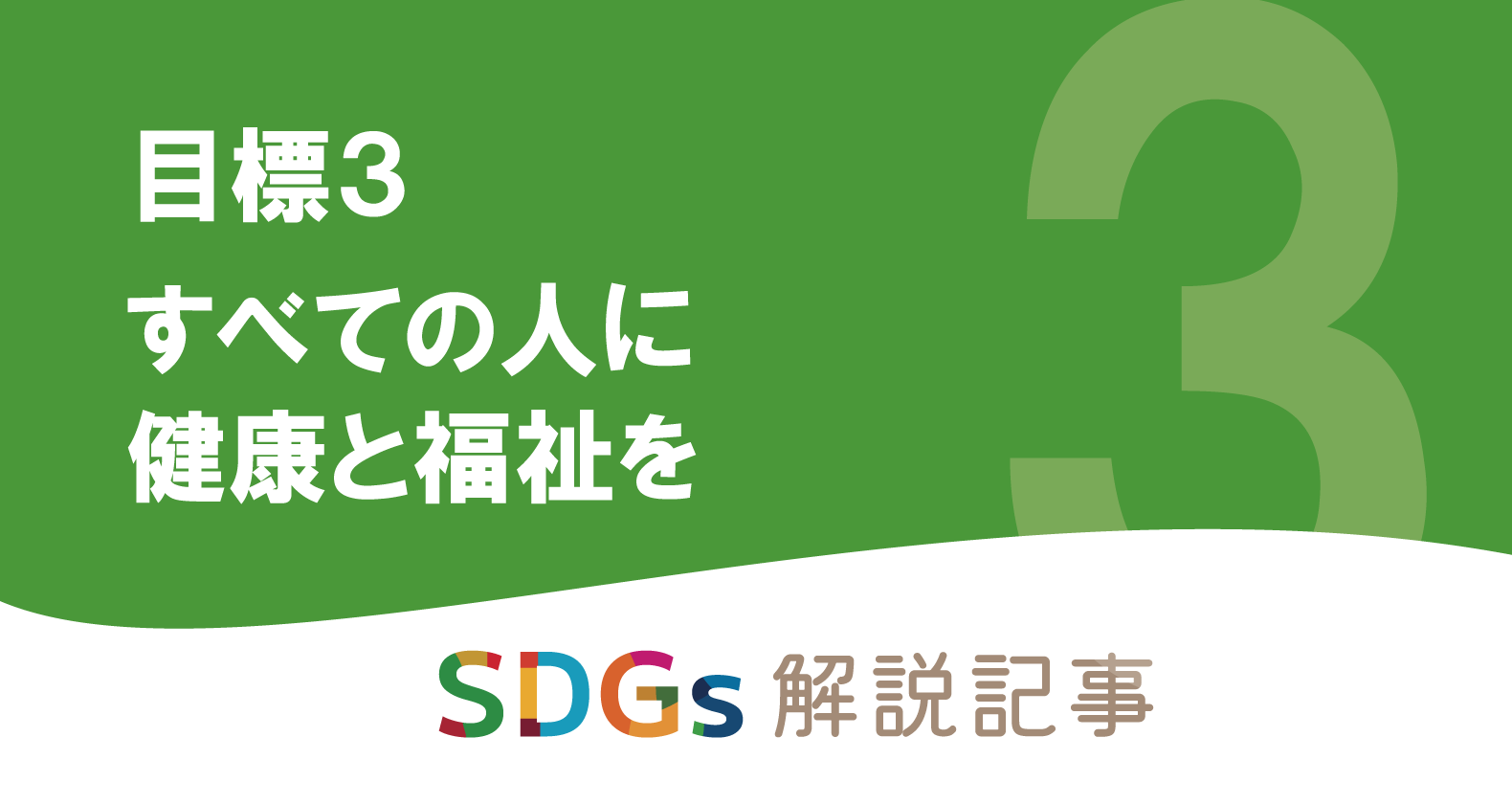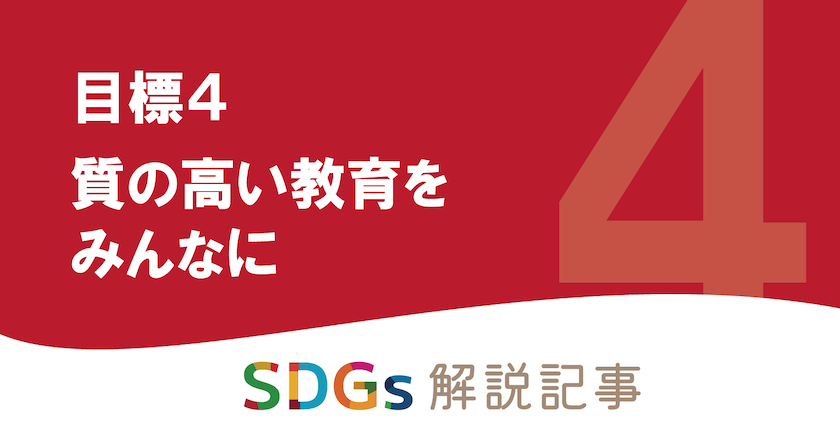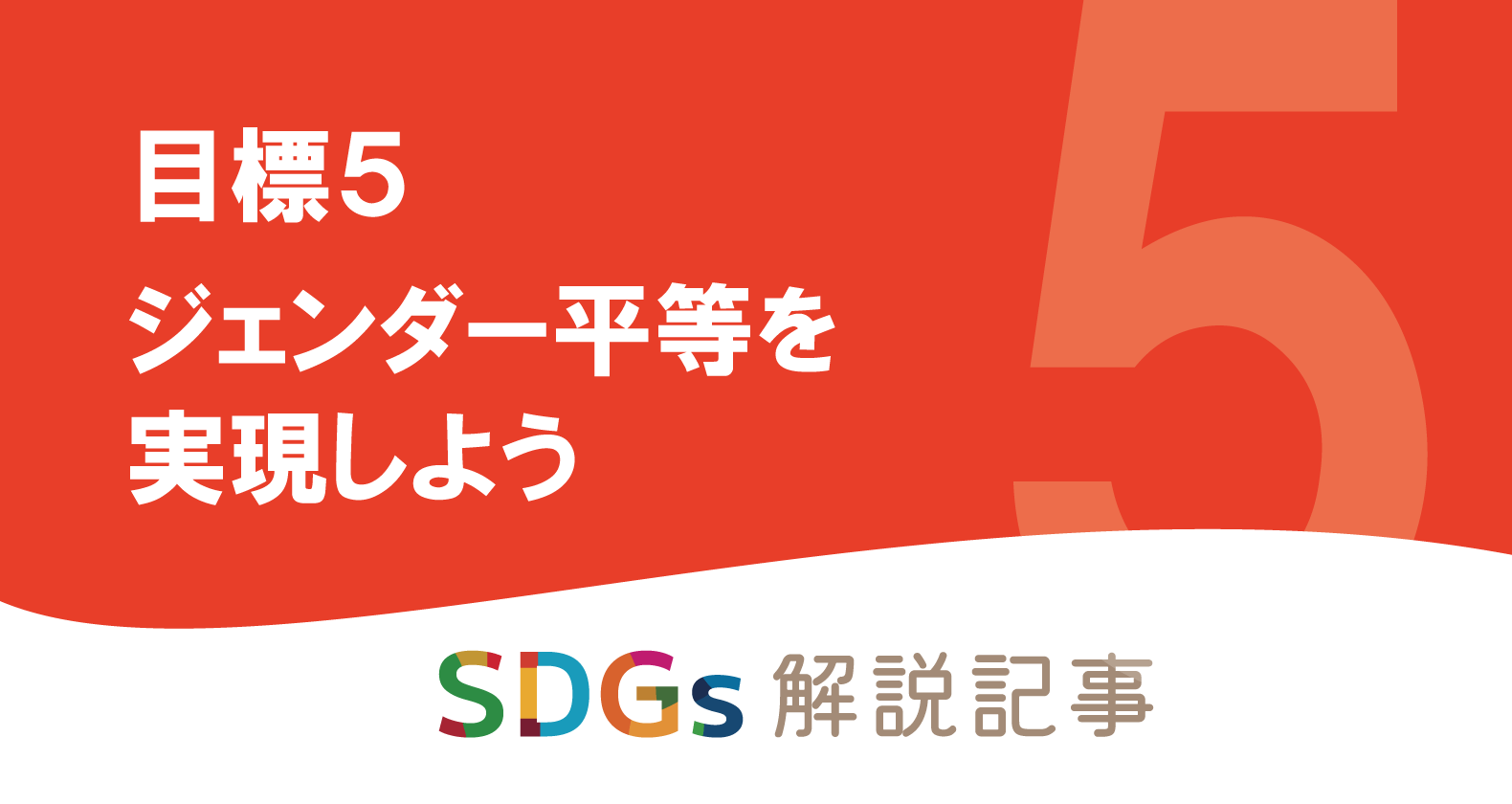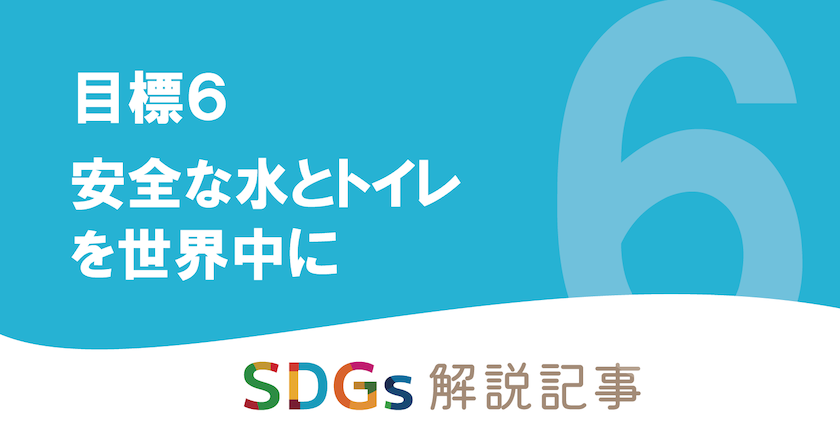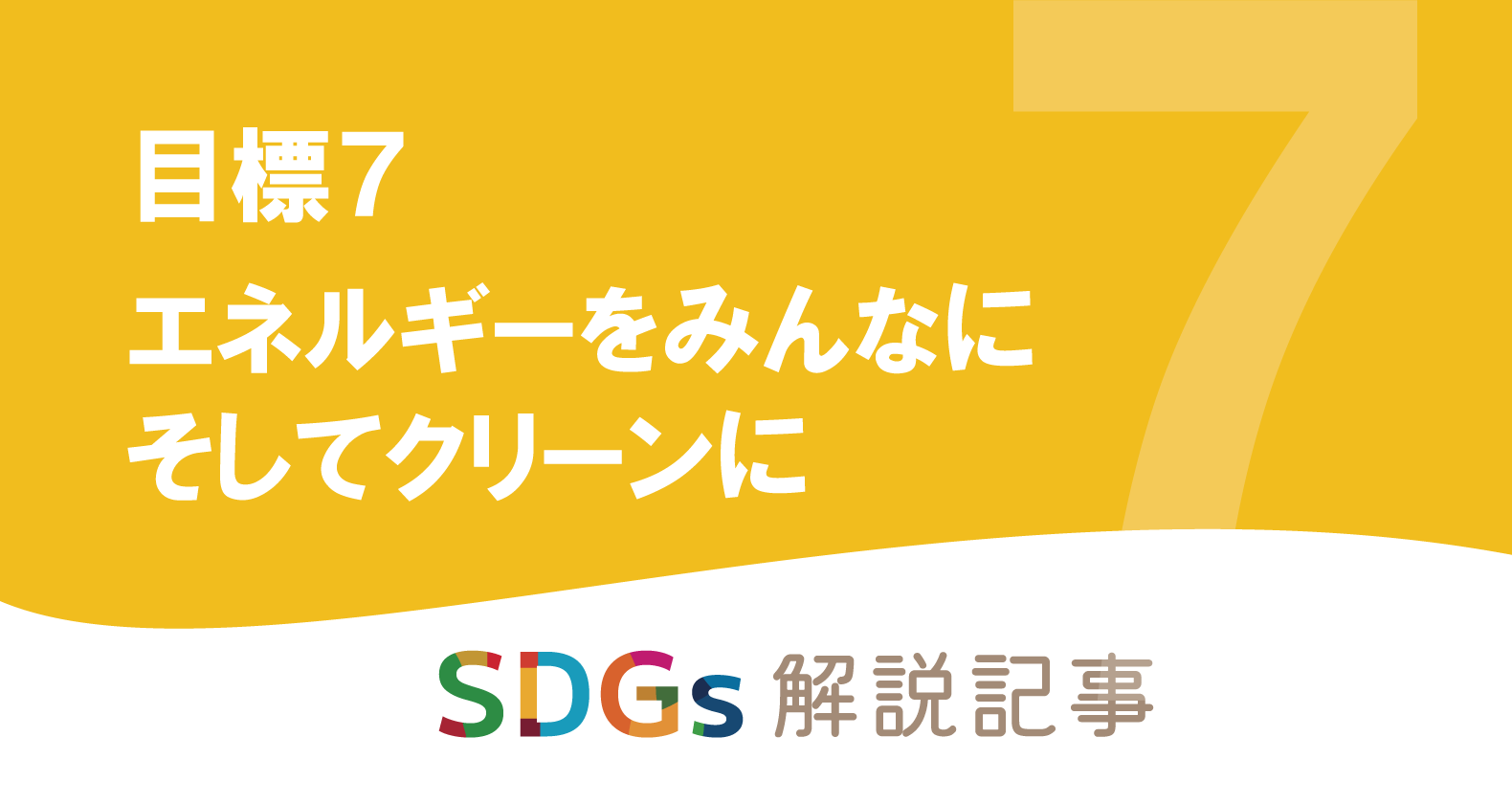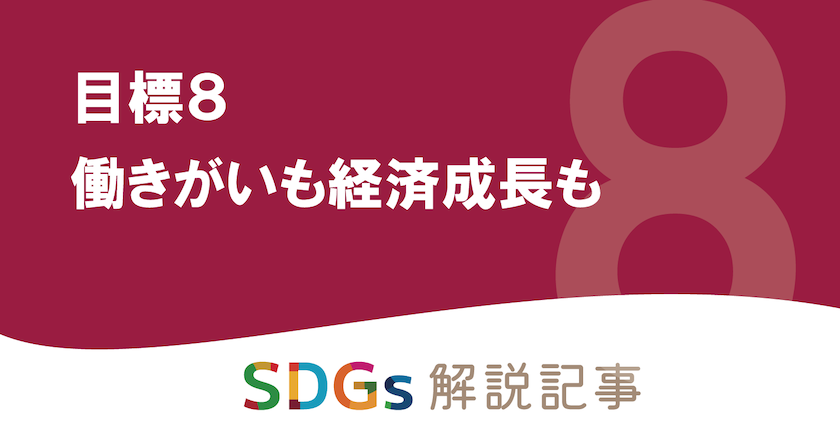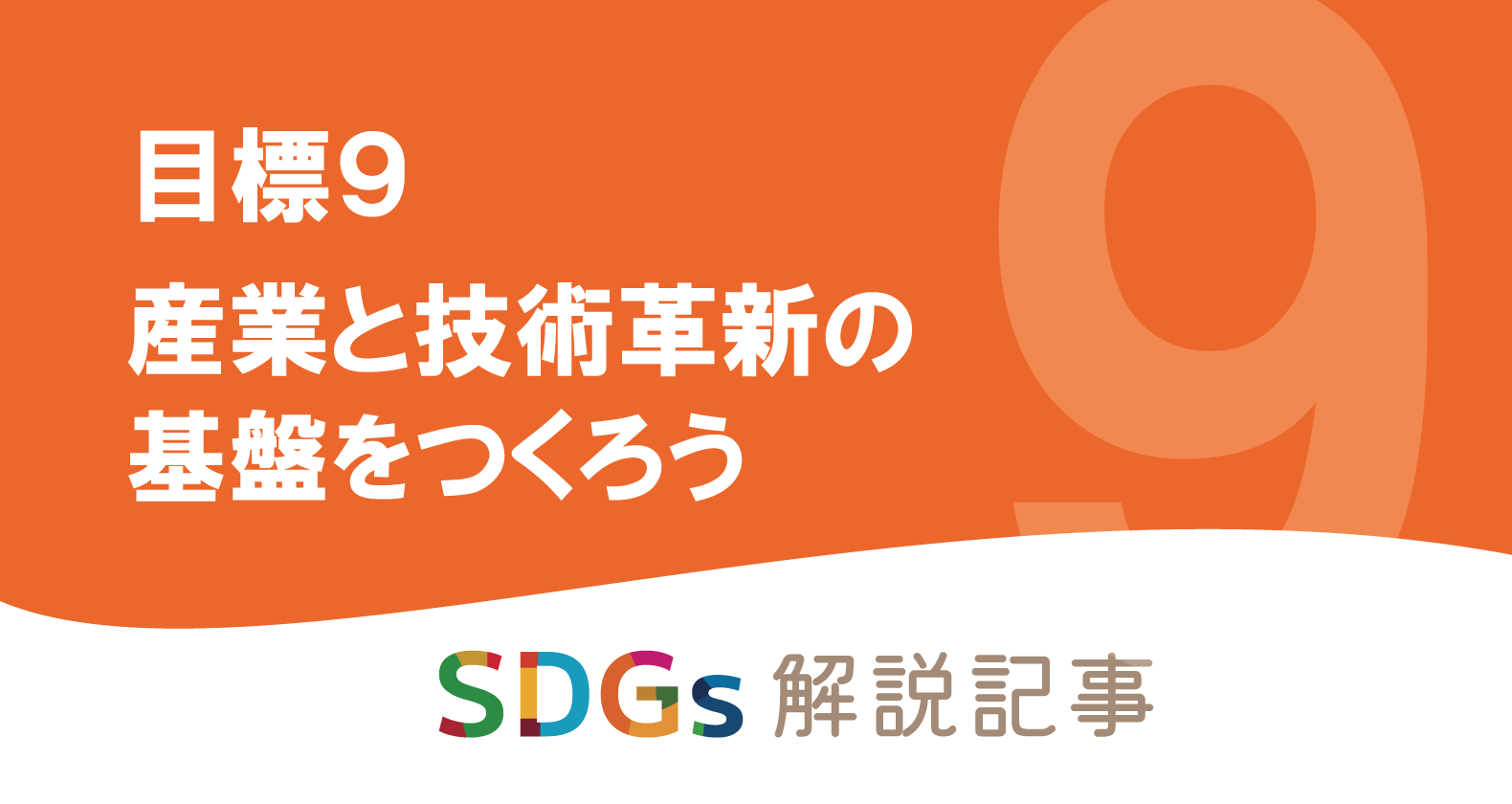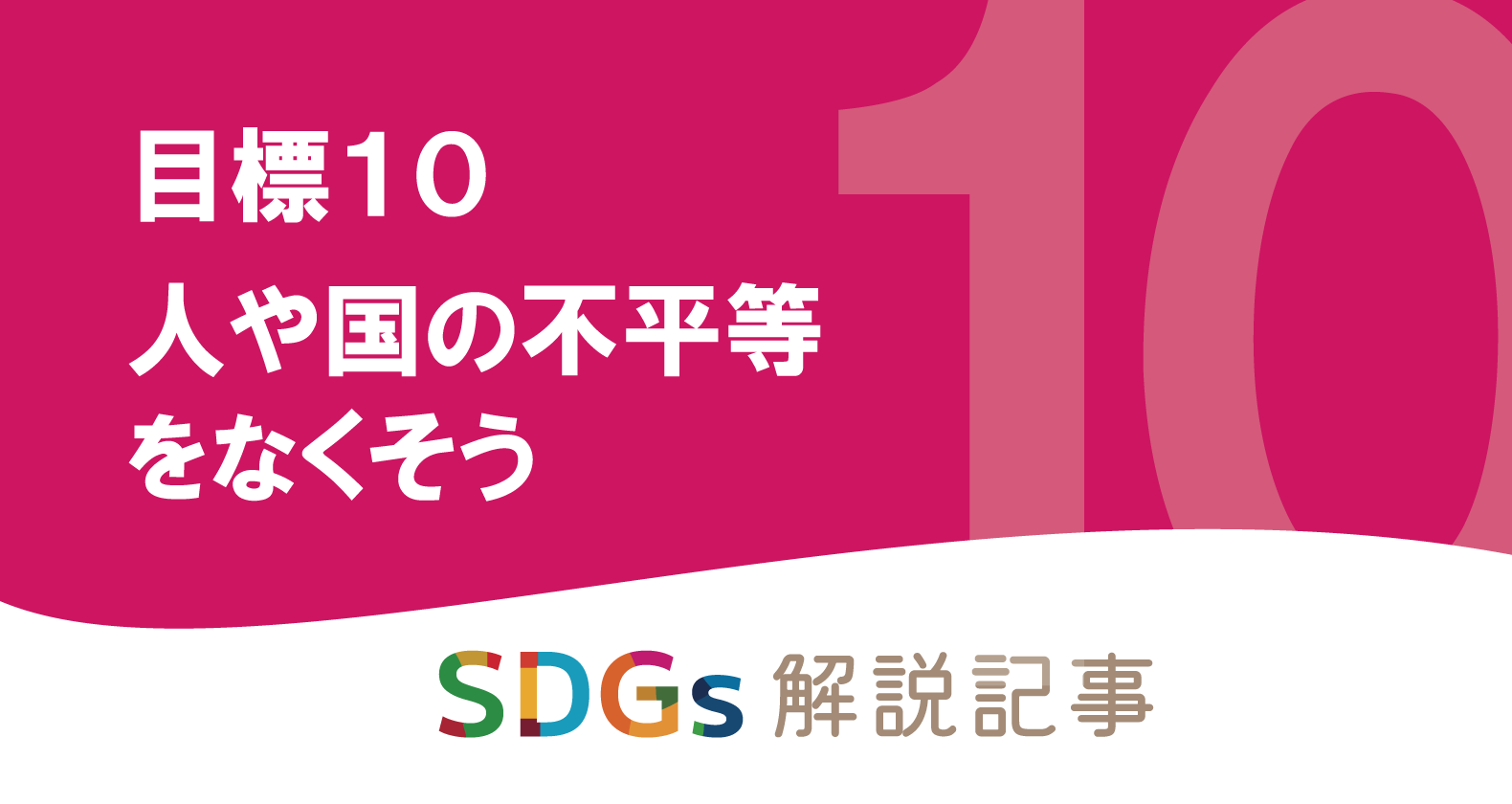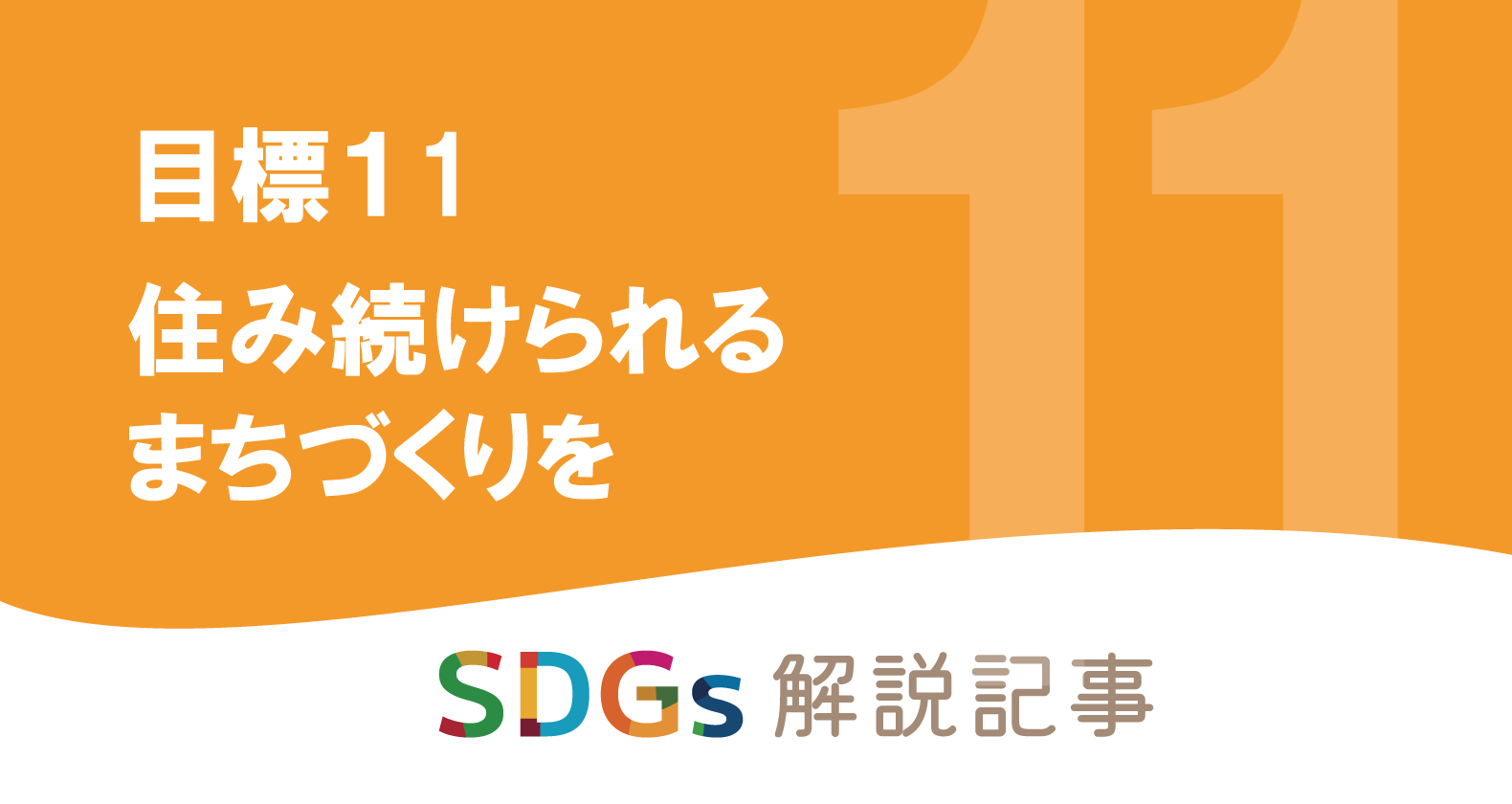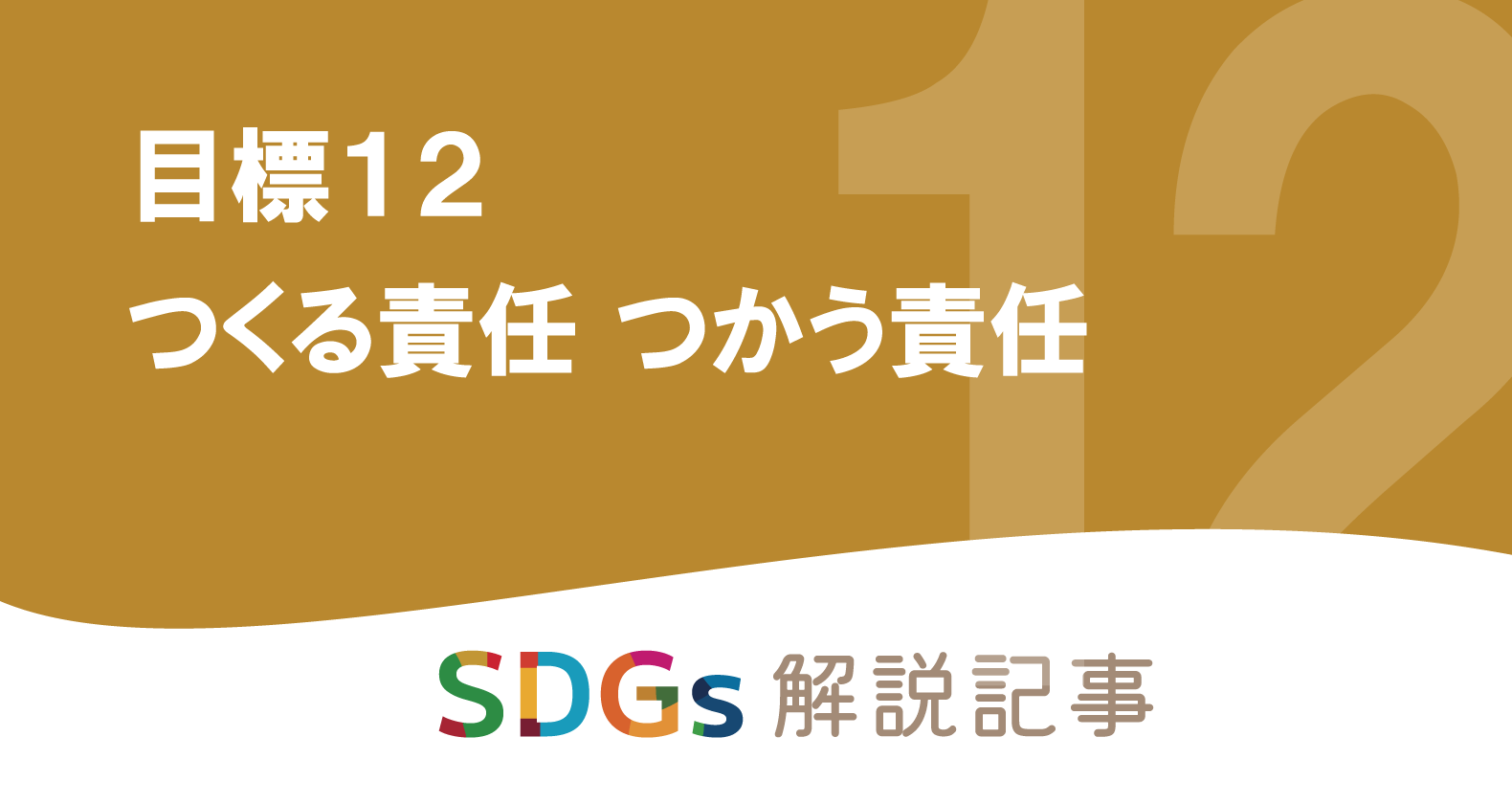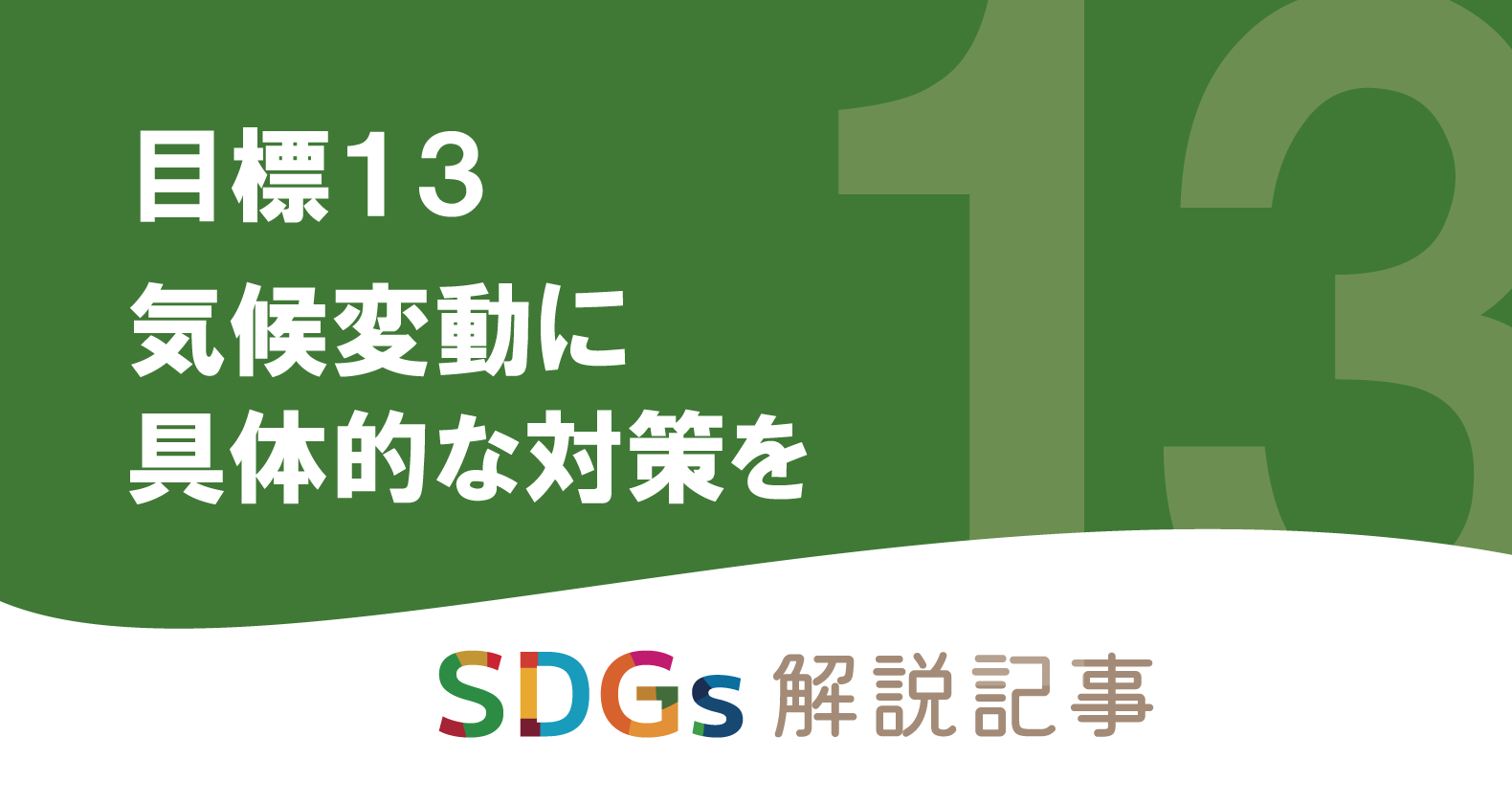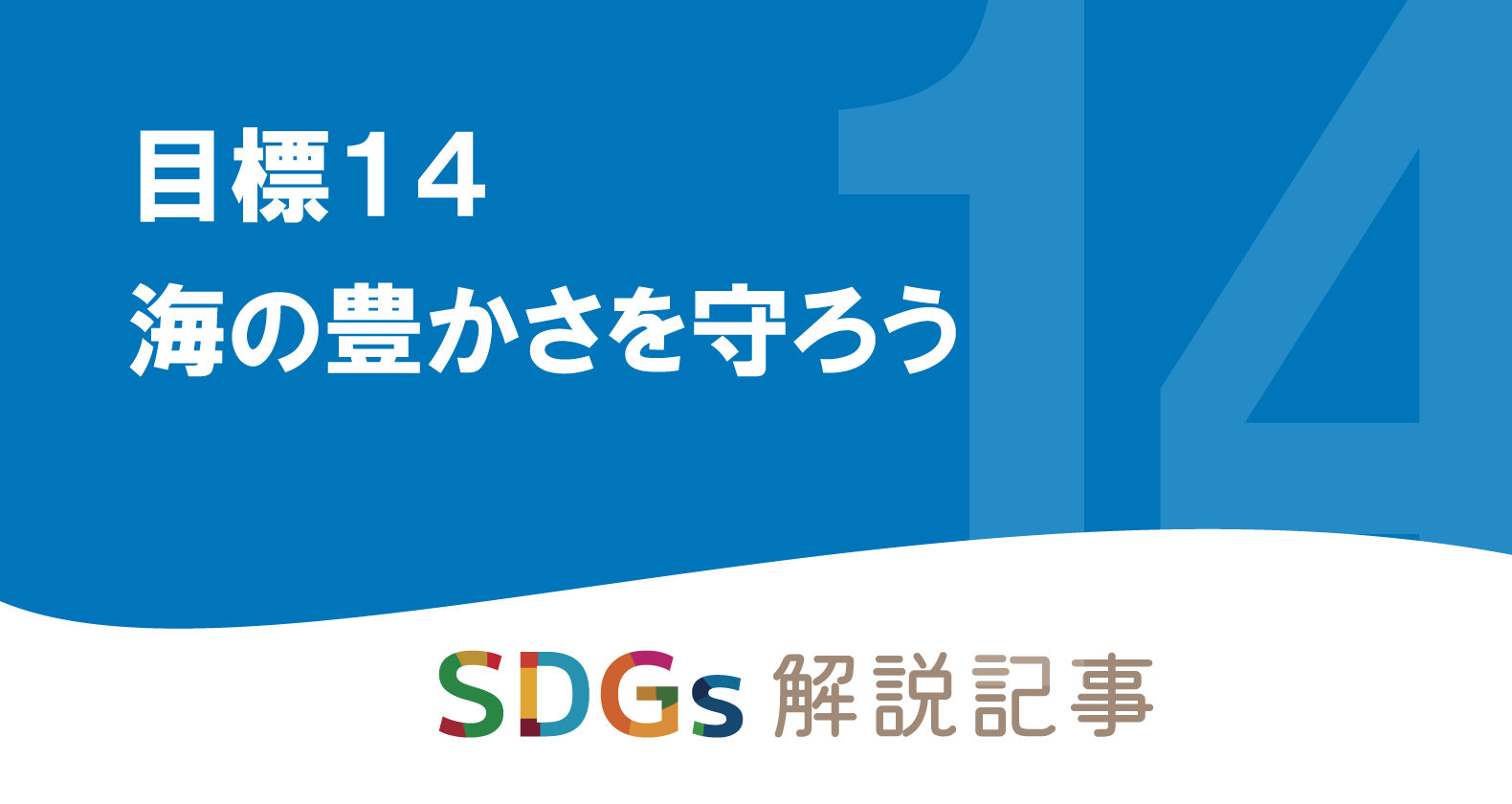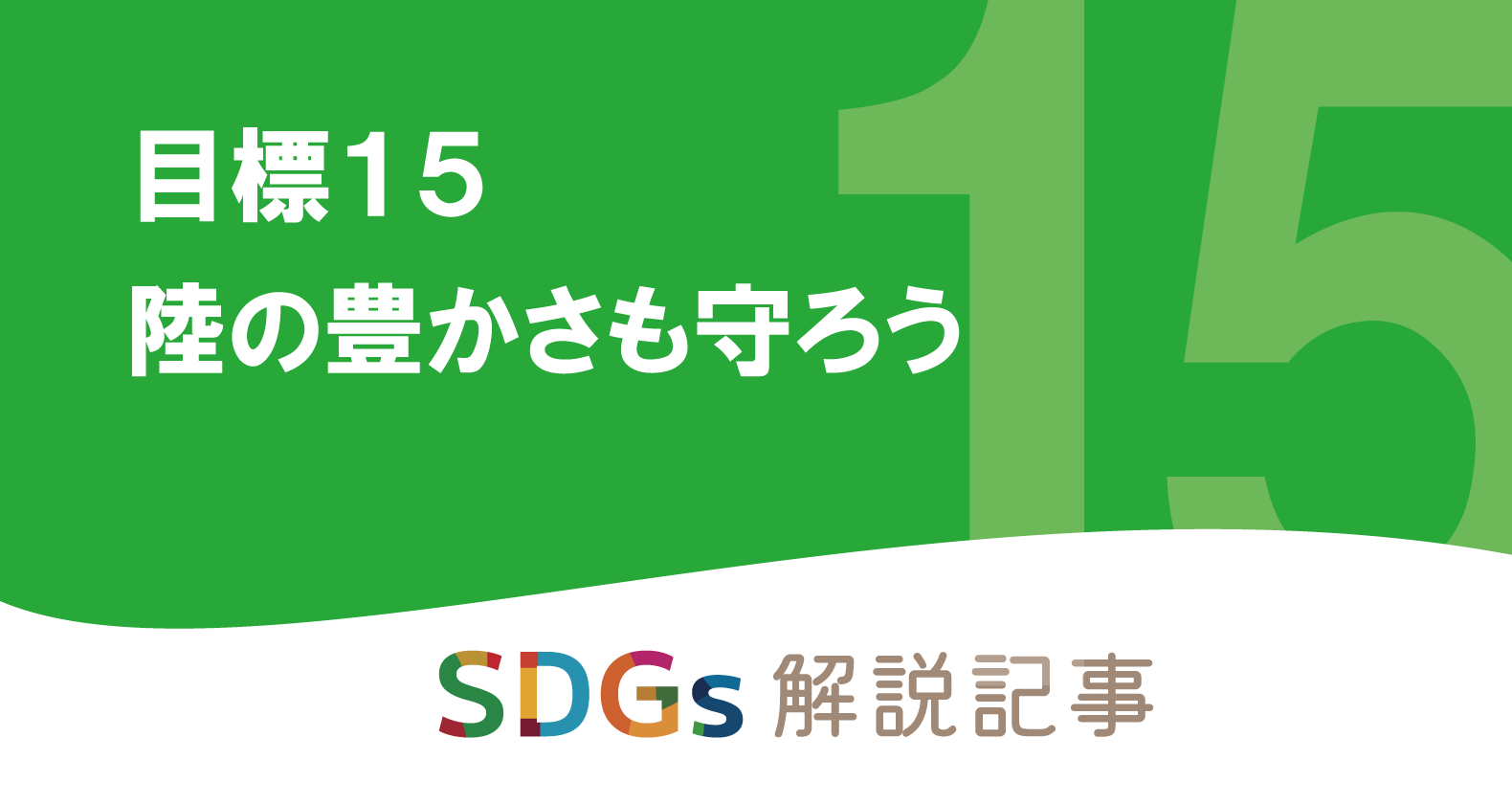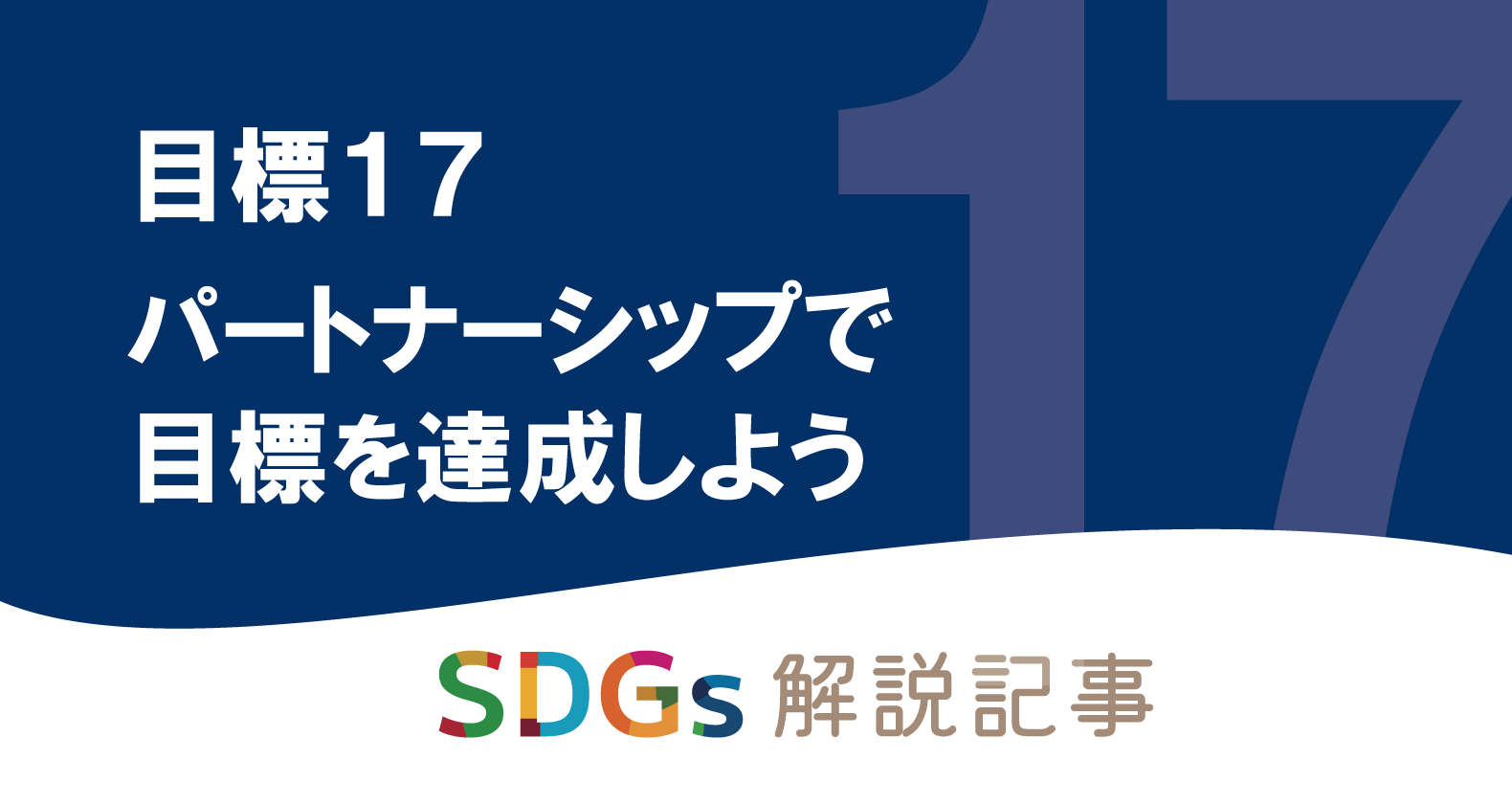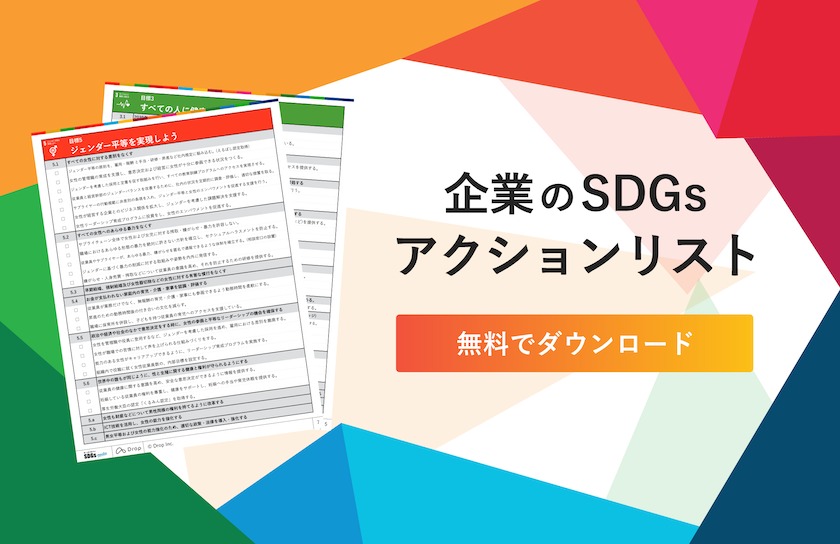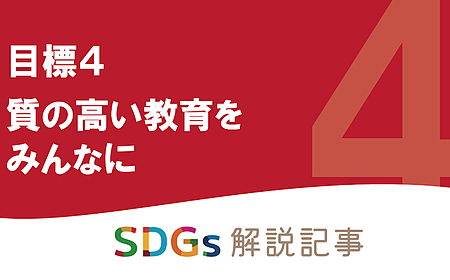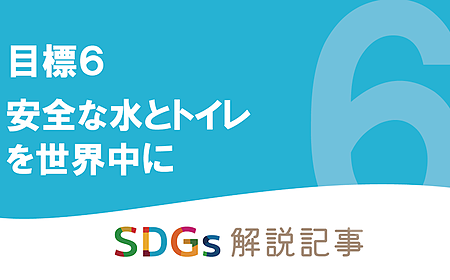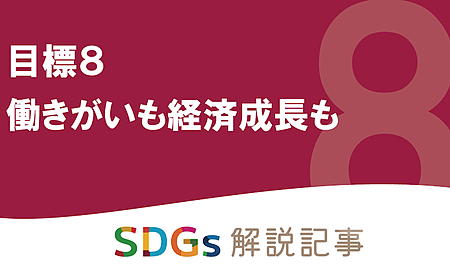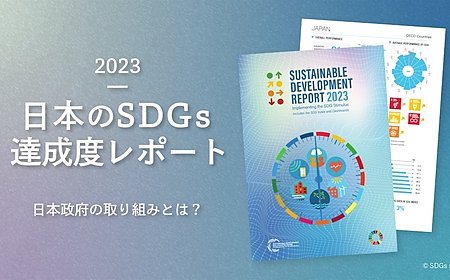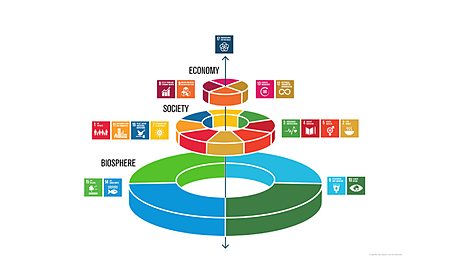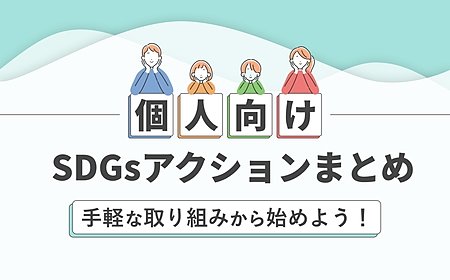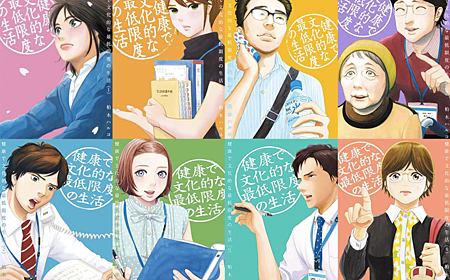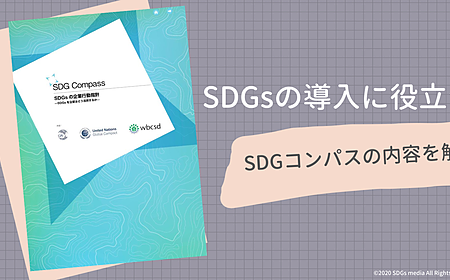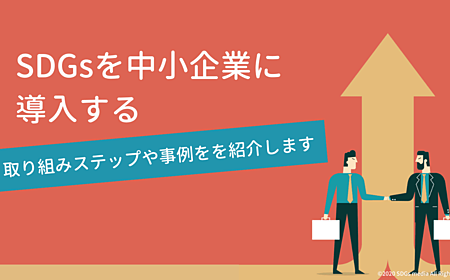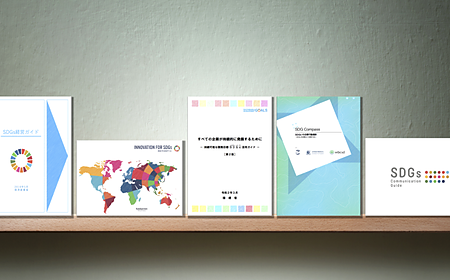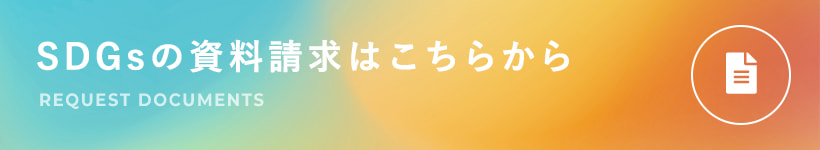SDGs目標1 貧困をなくそう を解説|世界と日本の課題とは
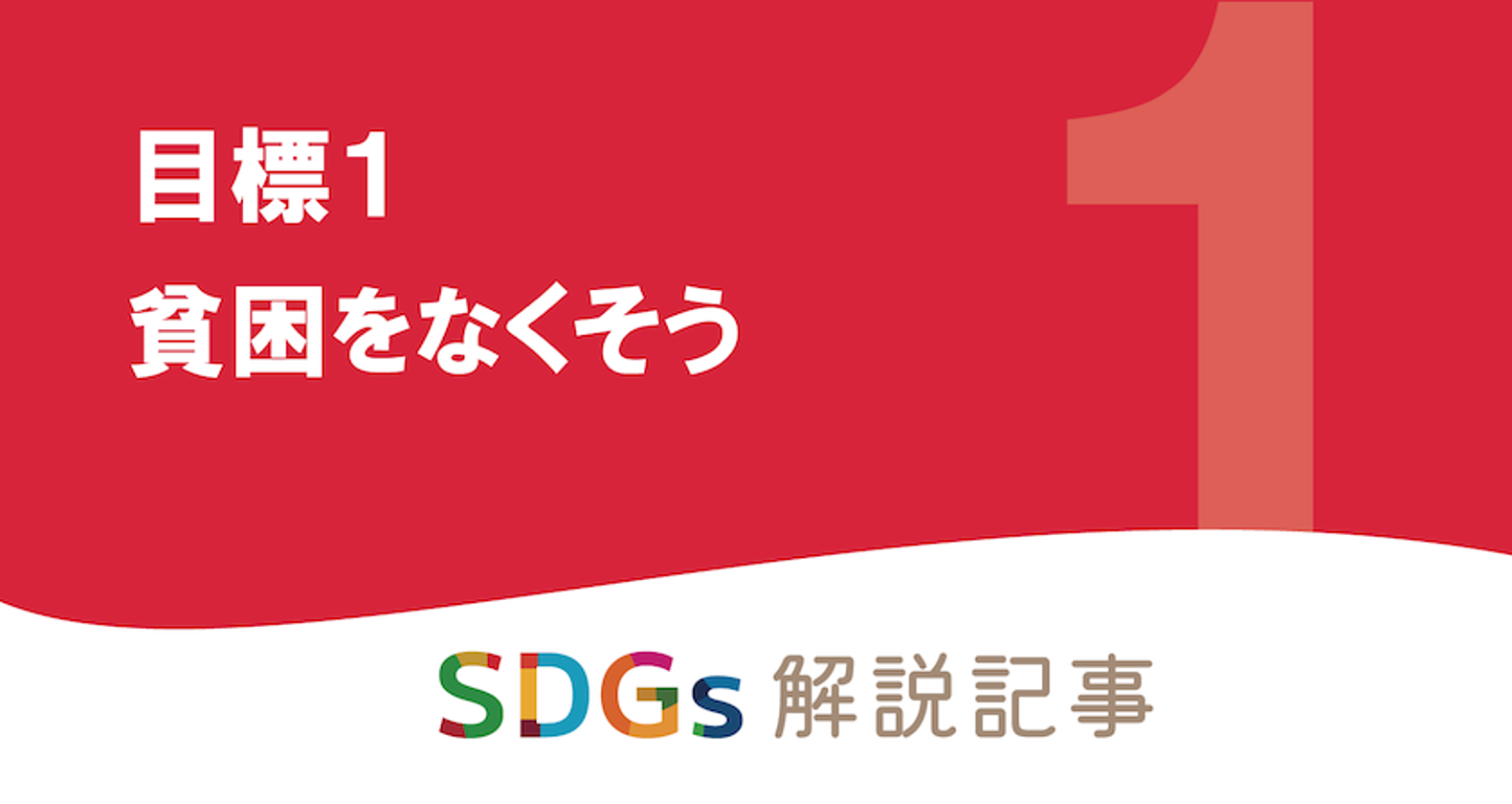
SDGsがネットやテレビで紹介されると、SDGsに関心を持つ人が増えていきます。SDGsの17種類の目標それぞれの内容を知って、自身で貢献したり会社や学校で取り組みを検討したりと具体的な行動を取る機会もあるでしょう。
SDGs目標1は「貧困をなくそう」。世界で最も取り組む必要がある課題の1つです。
最近では、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、貧困層は増加傾向にあります。しかし、どこか、日本とは関係ない問題と感じる方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、SDGs目標1の内容解説と、日本と世界の貧困状況、貧困から抜け出すことがいかに困難なのかなどについて解説します。
今回の記事はこんな人にオススメです
- 目標1の内容を詳しく知りたい
- 自分たちが目標1のためにできることを考えたい
- 子どもにわかりやすく説明したい
目次
目標1「貧困をなくそう」の概要
目標1は、貧困に関する内容が盛り込まれています。
掲げられたターゲット(具体的な課題)は7個。1日150円以下で生活する人をゼロにする、どこのどんな貧困も半分にするなど、世界のあらゆる場所で貧困をなくしていくための課題を挙げています。
貧困は単なるお金の援助だけで撲滅できるものではありません。貧困の根底にある原因から解消していく必要があります。
目標1では、稼ぐために必要なモノや知識を届ける、貧困層の多い開発途上国に十分な知恵や人材サポートをするなど、貧困層の経済的な自立を促す課題が含まれていることが特徴です。
目標1のターゲット一覧
以下の表でSDGs目標1のターゲット一覧を紹介しています。各ターゲットを読むとどんなゴール・課題が目標1に含まれるのかイメージがわくでしょう。
企業・個人でSDGsの達成に貢献する取り組みを始めるには、このターゲットから考えていくことがオススメです。そのうえで、SDGs media では、アクションを考える参考になる無料の資料『【17目標別】企業のSDGsアクションリスト|345種類の施策から自社の取り組みを探そう』を提供しています。取り組みを考える際はぜひご活用ください。
| 1.1 | 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 |
|---|---|
| 1.2 | 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。 |
| 1.3 | 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 |
| 1.4 | 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、 天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的 資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 |
| 1.5 | 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、 気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に 暴露や脆弱性を軽減する。 |
| 1.a | あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上 国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協 力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 |
| 1.b | 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 |
世界における貧困の状況

絶対的貧困
「貧困」とはどのような状態を指すのでしょうか。まずは、代表的な考え方の1つである「絶対的貧困」について紹介します。
絶対的貧困とは、国や地域の生活レベルとは無関係に、人間らしい生活を送るうえで必要な最低限の基準が満たされていない状態を指します。世界銀行は2015年に、「1日1.90ドル(日本円で約200円)以下で生活する層」を国際貧困ラインとして定めています。
世界銀行の発表によると、2017年に絶対的貧困状態にあったのは6億8,900万人(世界人口の9.2%)で、その60%以上がサハラ以南のアフリカの発展途上国で暮らしています。
貧困の影響は子どもの方が受けやすく、絶対的貧困の半数は子どもといわれています。親が経済的に困難な状態にあると、その子どもは十分な食事の摂取や医療を受けることができず、成長発達に支障をきたす可能性が高まります。
このような貧困状態で暮らす子どもは、早々に労働力として期待されるため、学習や進学の機会を喪失し、大人になっても低賃金の職にしか就けず、その子どもも貧困に陥るといった、世代を超えた貧困の連鎖が起きています。
経済的な困窮以外の指標
貧困は、必ずしも「経済的な困窮」のみを指すものではありません。貧困を多面的に捉えた「多次元貧困指数」という指標を紹介します。
多次元貧困指数は、国連開発計画により2010年人間開発報告書で導入され、教育や健康、生活水準などの多様な側面から貧困に苦しんでいる人の実態を浮きぼりにできます。
多次元貧困指数の指標一覧(10種類)
- 就学年数:就学経験年数が6年以上の世帯員がいない
- 子どもの就学:学校に通うべき年齢の子どもが就学していない
- 子どもの死:調査日までの過去5年間のうちに子どもが亡くなった世帯
- 栄養:調査日までの過去5年間のうちに子どもが亡くなった世帯
- 電力:電気の供給を受けていない
- 衛生:改善された下水設備がない、または改善された下水設備を他の世帯と共用している
- 安全な飲料水:安全な水が得られない、または安全な水を入手するのに往復30分以上かかる
- 床:家の床が泥、砂または糞である
- 炊事用燃料:糞、木材または木炭で料理をする
- 資産 ラジオ・テレビ・電話・自転車・二輪車・冷蔵庫・自動車・トラックのいずれも持っていない
※内閣府の子供の貧困に関する新たな指標の開発に向けた調査研究報告書 平成29年3月内の国連開発計画「多次元貧困指数 (MPI: Multidimensional Poverty Index)」を元にSDGs media が作表
貧困は単純に「お金が手に入れば脱出できる」というものではありません。貧困の背景には、さまざまな問題が複雑に絡まっています。
日本における貧困の状況

相対的貧困とは
日本の貧困問題を考えるうえで指標となる「相対的貧困」について紹介します。
相対的貧困とは、特定の国や地域の生活水準や文化水準で比較したとき、大多数より貧しい状態のことをいいます。具体的には、世帯所得がその国の等価可処分所得の中央値に満たない状態を指し、日本の相対的貧困率はOECD加盟諸国で7番目(2017年)に高いことがわかっています。
日本の場合、特に子どもの貧困率が高く、およそ7人に1人が相対的貧困に該当します。貧困状態にある子どもたちは、学業の時間を削ってアルバイトや家事をする、家計のために食費を切り詰める、金銭的な理由で進学をあきらめるなど、多くの人が享受している生活を送ることができません。
さらに、貧困は子どもたちに身体的・心理的な悪影響も及ぼします。たとえば、無茶な働き方による健康阻害、「自分が家族を支えなければならない」というプレッシャー、「なんで自分だけが」という不平等感からくる憤りなど、大きなストレスを抱えることになります。
日本の貧困の多くは、衣服や持ち物、住居など外見からは認知することが難しいため、支援の手を差し伸べにくく、社会課題となっています。
相対的貧困に陥る原因
相対的貧困に陥る代表的な原因を3つ紹介します。
- 事故やさまざまな事情で家族を失う
- 不景気で仕事を失う
- 災害などで財産を失う
これらの原因に共通するのは「いつ誰がなってもおかしくない」ということです。
病気や災害で家族を失う、パートナーと離縁し1人で子どもを育てる、不景気や事故で正規の職を失い非正規で働くなど、自分の力ではコントロールできない出来事により、生活が大きく変わる可能性があります。
貧困はけっして他人事ではありません。自分自身にも起こり得る身近な問題として、対策を考えていく必要があります。
関係性の貧困が日本で深刻化
貧困は、犯罪の発生にも影響します。法務省の平成30年版犯罪白書(2018年)によると、1998年以降の高齢入所受刑者数は増加傾向にあります。
高齢者による犯罪の原因は大きく3つあるといわれています。それぞれ上記の犯罪白書のデータとともに紹介します。
1:孤独感
高齢者の入所受刑者は、一般高齢者に比べ、配偶者と離別・死別した人が多く、男女ともに過半数を占めます。
2:経済的悪化
2017年の高齢入所受刑者のなかで職についていた割合は、男性が15.3%、女性が11.5%と非高齢入所受刑者(男性34.4%、女性20.0%)と比べて低い傾向にあります。
3:認知症
2015年に実施された調査では、13.1%(75歳から79歳の受刑者の25.6%、80歳以上の受刑者の28.6%)が認知症傾向にあるという結果が出ています。
高齢者の犯罪の根底には、地縁関係の希薄化にみられる「関係性の貧困」があり、再犯率の高さも問題視されています。
たとえば、2006年に起こった下関駅の駅舎全焼事件では、当時74歳の男性による犯行の動機は「刑務所に戻るため」でした。男性は過去に何度も放火事件を起こし、最初の事件の後に身内と絶縁してからは、犯罪と服役を繰り返し、計50年以上を刑務所で過ごしています。
こうした犯罪行為自体は許されることではありません。
しかし、経済的な課題を抱え、社会的にも孤立している元受刑者の社会復帰支援について考えさせられる側面もあります。男性は、下関駅に放火する数日前、生活保護の申請に行ったのですが、定まった住所がないことを理由に断られています。
頼る人もお金もない、それなら刑務所のほうがましだと、今回の事件を起こしています。
奨学金返済について考える
次は、若者の貧困について見ていきます。日本学生支援機構の調査によると、2018年度の大学昼間部に通う大学生のうち、2人に1人が奨学金を受けています。
奨学金は大きく分けて2種類、「給付型」と「貸与型」があります。給付型は返済が不要ですが、貸与型は卒業後に返済する義務があります。貸与型の奨学金は学生自身の名義で借りるため、少し極端な見方をすれば、250万円から300万円の借金をすることになります。
学生が奨学金を受給する理由は、おもに2つあります。
1つ目は、親の収入の減少。バブル崩壊以降、非正規雇用者が増加したことが関係していると考えられています。
2つ目は、教育費の負担率の上昇。労働者福祉中央協議会が2019年に発表した「奨学金や教育費負担に関するアンケート調査」によると、おおよそ3人に2人が子どもの教育費を負担に感じていると回答しており、子どもが大学・大学院生の場合、9割に達します。
さらに、同アンケート結果によると、毎月の平均返済額は約17,000円、平均返済期間は15年です。仮に、4年制大学に進学し、毎月10万円の奨学金を年利3%で受給した場合は、毎月約27,000円を20年間返済する必要があります。
厚生労働省が発表した令和元年賃金構造基本統計調査結果によると、大学卒の初任給は約21万円、手取りだと約17万円です。そこから、毎月2万円から3万円を奨学金の返済に充て、残りを住居費や食費などの生活費に回すとなると、けっして楽な生活はできません。
近年、若者の「ワーキングプア(働く貧困層)」も問題視もされています。昼間部に通う大学生の2人に1人が奨学金を受給している事実から、若者にとって身近な課題であることがわかります。
貧困から抜け出すことは簡単ではない

ホームレス状態から抜け出すことを考える
2021年に厚生労働省が実施した調査によると、日本全国のホームレス数は3,824人(男性3,510人、女性197人)とされています。2017年と比較すると、1,700人ほど減少しています。
一方で、2018年に東京都が実施した調査によると、安定した住居を持たずにネットカフェなどに寝泊まりしている人は、都内だけで一晩に4,000人いると推計されています。このような「見えないホームレス」の数を含めると、今も多くの人が不安定な居所で生活をしていることがわかります。
さらに、一度ホームレスの状態に陥ると社会復帰するのが困難になるという問題もあります。その背景には、仕事に就き住まいを確保する難しさがあります。
まず、安定した職を得るためには、住所や身分証、連絡先などが必要です。そのため、こういったものを保持していなければ、経済的な自立が阻まれます。
そして、住居を探すにも調べる手段がなく物件情報にアクセスできない、家を借りるために必要な保証人や初期費用を用意することができないためなどが理由で、契約まで至りません。
日本には、ホームレス状態にある人の自立を促すための生活保護制度などがあります。しかし、支援制度を利用するためには自分で申請する必要があり、情報にアクセスできない、あるいは頼る人がいない場合には、利用が難しいです。
一度ホームレスの状態に陥ると、こうしたさまざまな理由から生活を再建するハードルが高くなってしまいます。
親世代から続く貧困から抜け出すことを考える
親世代の貧困は子どもにも大きな影響を及ぼし、大人になっても貧困から抜け出せないといった、貧困の連鎖が世界各地で起きています。
貧困が連鎖する原因はさまざまですが、1つは教育の欠如と考えられています。たとえば、親が経済的に困難を抱えると、教育費が確保できないことや労働力として期待されることを理由に、子どもは学校に通うことが難しくなり、学習や進学の機会を喪失します。
そうすると、職業の選択肢も狭まり、低賃金の不安定な職に就かざるをえない可能性が高まります。そして、教育の重要性を知らないまま親となり、その子どもも学習の機会を喪失し困窮してしまうといった負のスパイラルに陥ります。
このように、貧困は世代を超えて連鎖しやすく、抜け出すことは容易ではなく、固定化していくケースが多々みられます。
他にもある目標1に関連するキーワード
今回の記事では解説しきれなかった、目標1に関連する課題のキーワードを簡単に紹介します。興味がある方は、ご自身で調べてみてください。
社会保護制度
「社会的保護の土台」は2016年にスタートした、国際労働機関(ILO)の主要プログラムのひとつです。包括的な社会的保護制度の確立や教育によって、貧困層を減らすことを目指しています。
2020年には、新型コロナウイルス感染拡大を背景に、ILOは発展途上国政府に対して早急な社会的保護措置の導入を呼びかけました。
具体的には、医療アクセスを保証するための国庫支出や、給付金と対象者数を拡大した現金支給の強化、休業補償や失業給付金を充実させることによる雇用・所得保護など、新型コロナウイルス流行という予期せぬ出来事に困窮した人々の生活の支援を促しています。
マイクロファイナンス
マイクロファイナンスとは、貧困緩和を目的とした小規模金融のことで、貧困層や低所得者を対象としています。寄付ではなく、あくまで融資のため、利用者は返済する必要があり、融資を受ける際には返済能力も問われます。
マイクロファイナンスは、貧困状態を一時的にしのぐためのものではなく、その先の経済的な発展と貧困からの脱出を見据えて、貧困層のビジネス成功を支援するための取り組みです。
貧困解消に向けたサポート
これまで紹介したように、貧困からの脱出は容易ではなく、中長期的なサポートが必要です。貧困の連鎖を断ち切るためには、子どもたちの教育が不可欠です。前述したように、日本では7人に1人の子どもが貧困家庭で生活をしています。
その多くがひとり親家庭であり、未来を担う人材育成のためにも、早急な対策が必要です。政府は、「子供の未来応援国民運動」を打ち出し、経済や教育の問題によって将来の可能性が閉ざされてしまう子どもたちを減らすための取り組みを進めています。
具体的には、「教育」「経済」「生活」「保護者の就労」の4つの軸から幼児教育の段階的な無償化や高等学校等就学支援金の給付、母子父子寡婦福祉資金の貸付、公的職業訓練といった支援制度の整備や導入を進めています。
また、「子供の未来応援基金」を創設して子どもたちの支援の輪を広げています。具体的には、企業や個人から基金への寄付を募り、公募申請を経て決定された子どもの支援団体に対する支援金として活用。2022年度には全国133団体が採択され、活動しています。
まとめ
ここまで、目標1の内容と関連する事例などを紹介してきました。日本に住んでいると、貧困をあまり身近に感じないという人も少なくありません。
しかし、日本の貧困は外見からはわかりにくく、7人に1人の子どもが貧困状態にあるという事実があります。
また、貧困に陥る原因は、突然の事故や病気で家族を失う、不景気や災害により職を失うなど、誰にも起こりうるものです。貧困を自分事として捉え考えていくことが大切です。
この記事を読んで学んだ貧困に関する取り組みを、周りに伝えたり自分でも取り組んだりしてみてください。
SDGs media では他の目標についても解説しています。気になる目標があれば、画像をクリックして解説記事を読んでみてください。各目標の詳細やSDGs自体について、企業とSDGsについてなど興味を持った方は、ぜひSDGs media で関連情報をご覧くださいね。
▶SDGsとは?17の目標内容と日本の政府・企業の取り組みを徹底解説 を読む
SDGsのターゲットから考える具体的な取り組み345選
SDGsの17目標・169のターゲットから企業が取り組めるアクションを345種類まとめました。本記事の冒頭で紹介した『SDGs達成に向けたビジネスアクションリスト』を入手する場合はこちら。
SDGs media 主催のセミナー情報
セミナーの開催予定・申し込みページ
SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。
過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報
過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。
▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら
| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |
|---|---|
| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |
| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |
| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |
| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |
参考サイト:
- JAPAN SDGs Action Platform | 外務省
- 相対的貧困とは?絶対的貧困との違いや相対的貧困率についても学ぼう|国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパン
- 子ども6人に1人が 極度の貧困で暮らす ユニセフと世界銀行による分析|unicef
- September 2020 global poverty update from the World Bank: New annual poverty estimates using the revised 2011 PPPs|World Bank Blogs
- 貧困の連鎖とは?その原因と貧困の連鎖を断ち切るための対策を考えよう|国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパン
- 第2章 2.2.2 国連開発計画 「多次元貧困指数 (MPI: Multidimensional Poverty Index)」|内閣府
- Ⅱ相対的貧困層について|内閣府(PDF)
- 日本大百科全書(ニッポニカ)「貧困率」の解説|コトバンク
- 相対的貧困とは何か?| Chance for Children
- OECD経済審査報告書日本April2017年概要|OECD(PDF)
- 平成30年版 犯罪白書 第7編/第3章/第4節/1|法務省
- 平成30年版 犯罪白書 第7編/第5章/第2節/コラム9|法務省
- 平成30年版 犯罪白書 第7編/第6章/第3節/1|法務省
- ひとりぼっちにしない――下関駅を焼失させた男性の社会復帰 | ヨミドクター(読売新聞)
- 平成30年度学生生活調査結果|日本学生支援機構(PDF)
- 「奨学金や教育費負担に関するアンケート調査」調査結果の要約|労働者福祉中央協議会(PDF)
- 「奨学金の返済がきつい」と感じる社会人が知っておくべき5つのこと。困った時に使える制度とは|マネコミ!
- 令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任|厚生労働省
- 【新社会人必見】初任給21万の手取りは18万以下!?|新宿相続税理士事務所
- ホームレス問題の現状 | ビッグイシュー基金
- ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について | 厚生労働省(PDF)
- 住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査報告書 | 東京都福祉保健局生活福祉部生活支援課(PDF)
- 「社会的保護の土台」をすべての人に|国際労働機関
- 【国際】ILO、途上国に対し包括的な社会的保護制度整備を要請。新型コロナ機に重要性再認識 | Sustainable Japan
- マイクロファイナンスの仕組み | マイクロファイナンスとは | Positive Planet Japan
- マイクロファイナンス 貧しい人々に、無担保で小額の資金を|IDE JETRO
- パンフレット|子供の未来応援国民運動(PDF)